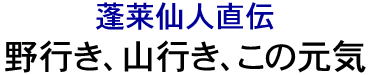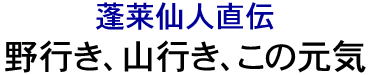|
第260回 (旧暦10月22日)
今年はまだギンナンが拾えます
仙人の「1万円生活」は昨日で一段落しましたが、
奥方のほうはこれからもその気でいるのでしょうか。
昨日、外出した折にイチョウの実(銀杏)を
たくさん拾って帰ってきました。
このイチョウの実は、デンプンとタンパク質に富み、
滋養強壮の薬果として古くから親しまれてきましたが、
実は日本在来の植物ではなく、中国から移入されてきたもので、
これを「ギンナン」と呼ぶのも、
漢名の「銀杏」の中国音「ギンアン」が転訛したものです。
ただし、渡来の起源については意外に詳(つまび)らかでなく、
『本草和名(ほんぞうわみよう)』(918年)とか
『和名類聚抄(わみょうるいじゅうしょう)』(932年)
といった平安時代の文献にはまだ登場していませんから、
早くても平安後期以降ということになるのでしょう。
また、鎌倉の鶴岡八幡宮の
本殿に上る石段脇には大イチョウがあり、
この木に隠れて待伏せしていた公暁(くぎょう)が
実朝(さねとも)を殺害したという言い伝えがありますが、
鎌倉幕府の史書である『吾妻鏡(あづまかがみ)』には
「石階の際に窺い来たり」と記述され、
このイチョウのことはなにも書かれていいのです。
となると、鶴岡八幡宮のイチョウの話もマユツバで、
鎌倉時代の初期にもまだイチョウは
渡来していなかった可能性も否定できないことになってきます。
聞くところによれば、「銀杏」を「ギンアン」と発音するのは、
中国でも北部の民族ということですから、
もしかすると「元」の時代(1279〜1368年)になってから
もたらされたのかもしれません。
それはさておき、漢方では種皮を取り去った実を
「白果仁(はくかじん)」と呼び、
滋養食や咳止めの薬としますが、
民間でも去たんや夜尿症にギンナン6〜7粒を
炒って食べるなどの療法があります。
また、葉っぱのほうは、フラボノイドのギンクゲチンなどを含み、
血管拡張や動脈硬化予防の作用がありますから、
健康茶にして飲用するとヨロシイ。
 |
| ギンナン |
|