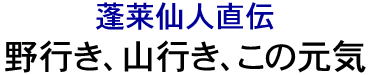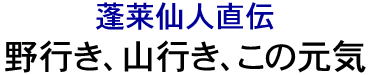|
第229回 (旧暦9月19日)
「村」の暮らしは1か月1万円がアタリマエ
思わぬ急用が出来たために
10日間あまり連載を休ませてもらいました。ゴメン。
また、10月1日から31日までの1ヶ月間を食費1万円で過ごすと
約束しましたが、これも半月スライドさせ、
10月15日より11月14日までの1ヶ月間に
仕切りなおすことになりましたので、合わせてご承知の程。
さて、その「1万円生活」ですが、テレビ番組では、
何日間かを水だけで過ごす挑戦者もあったようですから、
まことにもってご愁傷サマな話をいわなければなりますまい。
しかし、1ヶ月の食費を1万円で過ごすということは、
ちょっと都会を離れた農山村・漁村では現在でも
それほど突飛なことではなく、
それに近しい生活を成り立たせている人たちが
たくさん居るといっても過言ではないように思います。
それは、人間の暮らしというものは
そもそも自給自足経済によって成り立ち
支えられてきた歴史があって、集団生活の原型ともいえる
村社会では、今日でもそうした生活スタイルを基盤とした暮らしが
継承されているからにほかなりません。
たとえば、東京に隣接する人口1000人程度の
ある山村を例にとると、この村には肉も魚も置いていない
雑貨中心の小さなスーパーマーケットがひとつあるきりで、
八百屋とか肉屋とか魚屋とかいった
「食品」を商う店が1件もありません。
なぜかといえば、どの家も日常野菜は
自分の家の畠で作っていますし、
魚は村内を流れる渓流でヤマメやイワナといった川魚が釣れ、
海の魚に関しては、週に1回車でやってくる乾物を中心とする
巡回式の「魚屋」で普段は間に合っていますから、
八百屋や魚屋などを開いても、
そもそも「店」として立ち行かないのです。
つまり、この村の人たちは金を払って買い入れする食料といえば、
主食であるコメと、ハレの日などにたまに用いる
肉や海産の鮮魚くらいのものですから、
1か月の食費が1万円で納まるなどということは、
それこそアタリマエといわなければなりません。
したがって、こうした農村漁村の人たちが、
営んでいる基本的な生活スタイルを上手に組み込んでいけば、
街の中でも「1か月1万円生活」を実現することは
それほどムズカシイことではないのですゾ。
|