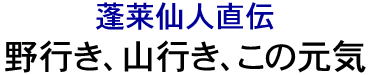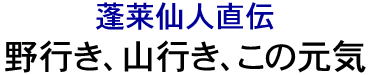|
第198回 (旧暦8月6日)
効果バツグンの「血止め草」
夏から秋にかけてのあいだ、
日当たりのよい丘陵や草原を歩いていて、
直立した茎先に径1.5cm内外の黄色の5弁花を何輪かつけている
30〜50cmほどの野草を見つけたら、
立ち止まってその葉っぱを調べてみてください。
そして、その葉っぱが、先端部がまるい被針形で、
基部が茎を抱くように対生しており、葉の表面に
シミのような黒点がいくつも透けて見えるようであれば、
それはオトギリソウだと判断して間違いはありません。
オトギリソウとは、日本全土に分布する
オトギリソウ科の多年草で、
古くから止血や消炎に卓効がある薬草として
重用されてきた歴史があり、
その効用から「チドメグサ」とも呼ばれています。
「オトギリソウ」という名前の由来は、
むかし、平安時代の花山天皇の御代に、
晴頼(せいらい)という鷹狩りの名人がおり、
この晴頼は傷ついた鷹をこの薬草で治すことを
門外不出の秘密にしていたものの、
晴頼の弟がこの秘密を他言したため、
晴頼は怒ってその弟を切り捨てた、という故事にちなむもので、
漢字では「弟切草」と記します。
漢方では、夏〜秋に採った全草を
「小連翹(しょうれんぎょう)」と呼び、
主として止血、消炎、鎮痛剤などに用いますが、
民間でも切り傷やすり傷、打ち身、虫さされなどに
生葉のもみ汁を塗布したり、全草をアルコールに漬けて
「オトギリソウチンキ」を作り、これを水虫に用いるほか、
神経痛やリウマチ、腰痛などの痛みに浴湯料とする、
などの療法が行われています。
ただし、このオトギリソウには、
紫外線を吸収して光増感作用を促進する
ヒペリシンという色素が含まれていて、
食用すると、そのヒペリシンが皮ふ組織の表層に及ぶことがあり、
このとき強い太陽の光を浴びると
皮ふの炎症を起すことがありますから、
食べたり、飲んだりしないほうがヨロシイ。
また、オトギリソウは変異性が強く、
地域変種を含めると日本だけで70種類以上及びますが、
原則的にどのオトギリソウでもおなじように薬用できます。
 |
| オトギリソウ |
|