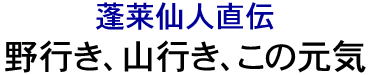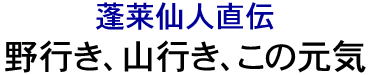|
第180回 (旧暦7月9日)
シソは仙人の常備薬
鎌倉では、市街地を一歩外れると、
まだ小さな畠地がたくさん見られます。
その鎌倉の畠で今いちばん目立つのは、
人の背丈ほどに生長したシソの姿でしょうか。
シソは、中国大陸中南部原産のシソ科の1年草で、
各地で広く栽培されるほか、一部の地域では野性化も見られます。
シソといえば、現在では梅やチョロギ、シバ漬けなどの
着色や香辛料として、もっぱら食用に使われていますが、
そもそもは、食用というよりも、
薬用や油をとる目的で移入されたものだったのです。
日本の油、とりわけ灯火用油の歴史を概観すると、
最初がゴマの油、次いでエゴマの油(荏油=えあぶら)、
そして、その荏油にとって代わったのがシソ油でした。
シソ油というのは、シソの種子から搾るのですが、
このシソ油には優れた抗菌作用が認められるため、
灯火用のほかにもしょう油の防腐剤として用いられてきました。
また、シソは全草にペリルアルデヒド、リモネンなどの
精油成分を含み、薬理実験でも解熱や抗菌の
作用があることが解っていますが、
漢方では、葉を「蘇葉(そよう)」、
果実を「紫蘇子(しそし)」と呼び、
発汗、解熱、咳止め、鎮痛、鎮静、利尿、健胃、解毒などに
用いられるほか、民間では、魚やカニなどにあたったとき、
葉を煎じて服用したり、種子3〜6gをそのまま服用したりする
療法があります。
仙人の場合には、そのシソを健康茶と薬酒、
そして薬湯などに利用していますが、
乾燥葉を作って保存しておくと、
そのいずれにも使えて重宝します。
乾燥葉の作り方は、果実をつけた地上部全草を採り、
1日ほど日に当てて半干し状態にした後、
日陰に吊るしてカラリと干し上げ、
細断して湿気のこない容器に入れて保管しておけばヨロシイ。
この乾燥葉を急須に入れてお湯を注げばシソ茶になりますし、
その煮出し汁を風呂に入れればシソ湯となり、
いずれも風邪の引き初めや安眠には顕著な効果が得られます。
一方、シソ酒のほうは、酒1.8Lに対し乾燥葉0.5L、
氷砂糖100gを加えて漬け込み(生葉の場合は1L)、1
0日後に中身だけを取り出して3ヶ月ほど寝かしておくと
スモークイエローに熟成し、
なかなかオツなリキュールに仕上がりますゾ。
 |
| シソの花 |
|