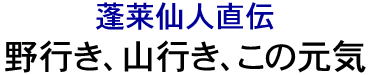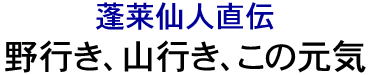|
第163回 (旧暦6月21日)
愛猫家にオススメの人畜兼用の薬木
今ごろの季節に山沿いの道路を車で走っていると、
枝先の葉だけが白くなっているつる性の植物が
ところどころに群れているのに気が付きます。
これはマタタビの木で、近くに寄って見てみると、
葉の腋からウメの花に似た白い花が
1〜3輪ずつ下向きにぶら下がっているのがわかるはずです。
「マタタビ」という風変わりな名前については、
疲れ果てた旅人がこの実を食べて元気を取り戻し、
また旅を続けた、という説がまことしやかに伝えられていますが、
実際にはどうやらアイヌ語の
「マタタムブ」から由来したものと考えられます。
アイヌ語では、「マタ」は「冬」、
「タムブ」は「亀の甲」の意味ですから、
おそらくマタタビの虫えい果の姿から
そう呼ばれるようになったのでしょう。
マタタビの花には、つぼみのころにマタタビタマバエが
産卵することが多く、この幼虫が入った果実は
亀の甲のような姿をしたデコボコの虫こぶ果になるのです。
この虫が入った虫えい果は食べられませんが、
(正常果は生食もできる)、おもしろいことに、
薬理的効果では虫えい果がダンゼン勝り、
漢方では、熱湯殺虫してから天日乾燥させた虫えい果を
「木天蓼(もくてんりょう)」と呼んで、
鎮痛や保温の薬として利用されるほか、
民間でもマタタビ酒を作り
(酒1.8Lに対し、虫えい果1L、氷砂糖100g)、
神経痛、リウマチ、痛風、冷え性、強壮などに
飲用する習慣があります。
マタ、マタタビの果実と葉に含まれる27種類の
イリドイド化合物のうちには、
イリドミルメシンなどのネコ科の動物が好む成分が
数種類あるため、ネコにこれを与えると陶酔状態になり、
弱っていたネコも元気を取り戻します。
つまり、人間にもネコにも効くフシギな薬草というわけですから、
ネコ好きの人は、今年の秋にはゼヒ、自分と愛猫の健康のために、
このマタタビの虫えい果を採りに行くことです。
ただし、マタタビの葉の白変現象は、花期を過ぎると終わり、
果実のころには再び緑色に戻っていますから、
マタタビの木の所在を覚えておくなら今のうちですゾ。
 |
 |
| マタタビの葉と花 |
マタタビの実 |
|