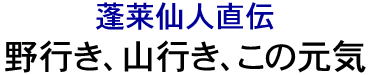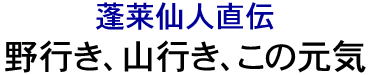|
第80回 (旧暦3月20日)
胃潰瘍に卓効のあるアカメガシワ
いま鎌倉の山ではアカメガシワの紅い新芽が目につきます。
アカメガシワというのは、トウダイグサ科の落葉高木で、
名前のごとく新芽や若葉のうちは紅い色をしているため、
新緑のなかでよく目立つからです。
アカメガシワという名称は「赤い芽の柏」という意味ですが、
実際には柏の仲間ではなく、
葉の形も柏と似ているわけではありません。
それなのにナゼ「赤い芽の柏」と
呼ばれるようになったかといえば、
この成葉は大型になり、
古い時代にはこの葉っぱに飯を盛ったり、
食べ物を包んだりして、
柏餅に使う柏の葉とおなじような
利用のされ方をしてきたからでした。
そのため、西日本の各地では、
今でもアカメガシワのことを「サイモリバ(菜盛葉)」とか
「ミソモリバ(味噌盛葉)」、
また「ボンガシワ(盆柏)」などと呼び、
神仏への供え物をこの葉に盛ったりする習慣が
残っている地域があります。
草木の葉には防腐作用や殺菌作用を持つものが
たくさんありますから、
おそらくアカメガシワの葉にもこうしたはたらきがあって
食べ物を長持ちさせる効果があるにちがいありません。
実は、アカメガシワの葉や樹皮には、
タンニンのはか、イソクマリン系物質のベルゲニンや
フラボノイドのルチンなどが含まれていて、
主として胃潰瘍や十二指腸潰瘍の民間薬として
利用されてきた歴史がありますが、
臨床試験の結果、実際に胃潰瘍に効果があることが判明し、
現在ではこの樹皮成分を主原料とした
胃潰瘍の治療薬が市販されているのです。
ちなみに、仙人の経験でも、
胃潰瘍を患った友人にアカメガシワの樹皮を乾燥して
お茶代わりに飲用することをすすめたところ、
潰瘍による出血がピタリと収まって
感謝されたことがありますから、
心あたりのある人は一度試してみてはどうでしょうか。
また、痔疾(切れ痔)や切り傷・すり傷、はれ物などには、
葉の煮汁を加えて入浴したり、
この煮汁で患部を洗ってやると効果があります。
 |
| 名前のごとく新芽が赤い色をしているアカメガシワ |
|