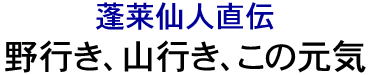
蓬莱仙人・大海淳さんの
身体にいい話
|
第72回 (旧暦3月12日) 関東地方南部ではヤマザクラとソメイヨシノも盛りを過ぎて、 ヤエザクラにも、関山、東錦、松月、天ノ川など 桜湯は、お見合いなど祝いの席に出される花茶ですが、 一方、花酒のほうは、つぼみ〜半開の花を摘み、 また、夏季に桜(どのサクラでもよい)の樹皮を剥いで、
|
| ←前回記事へ | 2003年4月13日(日) | 次回記事へ→ |
| 過去記事へ | ホーム |
最新記事へ |
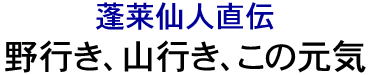
蓬莱仙人・大海淳さんの
身体にいい話
|
第72回 (旧暦3月12日) 関東地方南部ではヤマザクラとソメイヨシノも盛りを過ぎて、 ヤエザクラにも、関山、東錦、松月、天ノ川など 桜湯は、お見合いなど祝いの席に出される花茶ですが、 一方、花酒のほうは、つぼみ〜半開の花を摘み、 また、夏季に桜(どのサクラでもよい)の樹皮を剥いで、
|
| ←前回記事へ | 2003年4月13日(日) | 次回記事へ→ |
| 過去記事へ | ホーム |
最新記事へ |