温泉ライターが取材で拾った
ほっこり心が温まる湯浴み話
| 第53回 温泉発見人、御三家の残る1人は、 建久4(1193)年、鎌倉幕府が開かれた翌年、 草津温泉へ何度も行ったことのある人でも、 同じ頃、中之条町の沢渡(さわたり)温泉にも頼朝は訪れています。 温泉街の中心、共同浴場の隣に建つ |
| ←前回記事へ |
2012年5月30日(水) |
次回記事へ→ |
| 過去記事へ | ホーム |
最新記事へ |
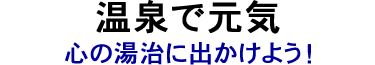
温泉ライターが取材で拾った
ほっこり心が温まる湯浴み話
| 第53回 温泉発見人、御三家の残る1人は、 建久4(1193)年、鎌倉幕府が開かれた翌年、 草津温泉へ何度も行ったことのある人でも、 同じ頃、中之条町の沢渡(さわたり)温泉にも頼朝は訪れています。 温泉街の中心、共同浴場の隣に建つ |
| ←前回記事へ |
2012年5月30日(水) |
次回記事へ→ |
| 過去記事へ | ホーム |
最新記事へ |