温泉ライターが取材で拾った
ほっこり心が温まる湯浴み話
| 第52回 温泉発見人の御三家2人目は、 弘法大師といえば、「弘法水」が有名です。 弘法大師が発見したとされる温泉は、 〜昔、昔。 このお坊さんが、有名な弘法大師だと知った村人たちは、 これが、昔から川場温泉が「脚気川場」といわれるゆえんです。 |
| ←前回記事へ |
2012年5月26日(土) |
次回記事へ→ |
| 過去記事へ | ホーム |
最新記事へ |
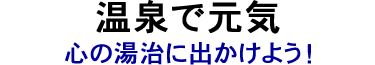
温泉ライターが取材で拾った
ほっこり心が温まる湯浴み話
| 第52回 温泉発見人の御三家2人目は、 弘法大師といえば、「弘法水」が有名です。 弘法大師が発見したとされる温泉は、 〜昔、昔。 このお坊さんが、有名な弘法大師だと知った村人たちは、 これが、昔から川場温泉が「脚気川場」といわれるゆえんです。 |
| ←前回記事へ |
2012年5月26日(土) |
次回記事へ→ |
| 過去記事へ | ホーム |
最新記事へ |