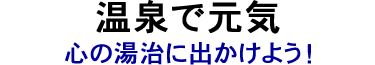|
第20回
目で楽しむ温泉
「昭和50年代、にごった湯は汚いと敬遠されたことがあり、
温泉をろ過して使おうかと考えたこともありました。
今となれば、かたくなに守り通して良かったと思います」
そう言ったのは、赤城山のふもとに湧く
梨木温泉の一軒宿
「梨木館」の女将、深澤正子さんでした。
開湯1200年。
鉄分を多く含む茶褐色のにごり湯は、
今でこそ温泉ファンに人気がありますが、
「お湯が腐っている」「浴槽の掃除をしていない」と、
お客に理解してもらえない時期があったといいます。
温泉には、2つと同じ成分の温泉はありません。
温泉法で定められた泉質名が同じでも、
何種類もの成分が溶け込んでいるため、
色もにおいも異なります。
硫黄成分が多いと乳白色ににごり、
鉄分が空気に触れると
黄緑色〜茶褐色に変色します。
またカルシウムやマグネシウムの含有によっては、
光の加減や時間の経過で色を変える温泉もあります。
これを私は「変わり湯」と呼んで楽しんでいます。
群馬県東吾妻町の鳩ノ湯温泉の一軒宿
「三鳩樓(さんきゅうろう)」の湯は、
何度訪ねても色が違います。
白かったり、黄色くなったり、青くなったり、
季節や天候によって毎日色を変えるのです。
「まれに無色透明になる」と、主人の轟徳三さんは言いますが、
私はまだ一度も出合ったことがありません。
群馬県前橋市(旧粕川村)の一軒宿、
滝沢温泉「滝沢館」の露天風呂の湯も摩訶不思議です。
源泉の温度が約25度と低いため、
浴槽に満たしてから加熱しているのですが、
最初は無色透明、しばらくすると黄褐色になり、
やがて白濁を始めます。
時間が経過すると半透明になり、また無色透明へと戻っていきます。
まるで変わり玉のように、コロコロと色を変えるのです。
温泉が時間の経過とともに変色するのは、
湯が空気に触れ酸化している証拠です。
ですから、こんな時は湯口に竹樋(たけどい)を渡して、
新鮮な源泉を流し入れてやります。
すると、不思議不思議、ふたたび黄褐色へとにごり始めます。
温泉には“劣化を楽しむ”という妙味もあるのです。
|