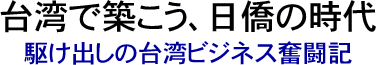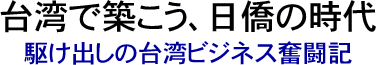|
第123回
結果思考ということ
この間のニュースで、
「営業成績によって増減する給与制度で、
6月の手取り額が約2万2000円となった
富士火災海上保険(東京)の男性社員(52)が15日、
生存権を定めた憲法に違反するなどとして、
3−5月の平均給与約21万9000円などの支払いを求める仮処分を
東京地裁に申し立てた。」
という記事が目を引きました。
この社員の言い分が法的に妥当かどうかは、
高島弁護士にお尋ねしたいものですが、
一体どうしてこうなってしまったのでしょうか?
同社が成果主義を導入したのは2000年といい、
すでに5年が経過しています。
この男性は勤続23年の営業担当ということだそうです。
長年会社に尽くしてきたのに、これではヒドすぎる、
ということでしょうか?
本人にも問題ありそうですが、
経営者にはもっと問題がありそうです。
松本順市という人事コンサルタントの方が、
「人事制度は社員を成長させる仕組み」というメルマガのなかで、
「『評価の違いによって昇給に差をつけたい』
なんて、トンでもない」
と仰っています。
「こんなことを社内で発表するから組織風土が壊れるのである。
昇給・評価に差がつかないように、
つまり全員が高い昇給になるよう教育指導するのが
上司(経営者)の仕事である。」
と書いています。
会社の目的は全社員一丸となって社会の役に立つこと、
それは利益計上という結果によって証明されるわけですから、
経営者はどうしたら結果を出せるかを、自ら示し、
社員の皆さんに納得してもらい、
かつ実行してもらう必要があります。
その会社の方向性や文化には
全てのヒトが適合するわけではありません。
途中から修正するなら尚更です。
合わないヒトには、そのことをキチンと示し、
別の道を選択してもらうことも経営者の大切な務めです。
制度導入から長年経過してこの結果では、お互い浮かばれません。
かくいう私も、
浪花節的な台湾人社員との意思疎通に苦労しています。
「がんばっているのになぜ他の社員より給料が低いのか?」
「昔からいる社員をなぜ冷遇するのか?」
結果志向、自分自身に対する警句と受け取っています。
|