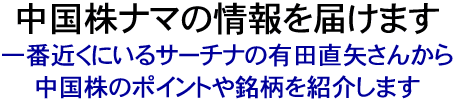|
第449回
一つのPlanに二つのDo:際立つ「和諧」の重要性
第11次5カ年規画(2006年−2010年)の
骨子となる中国共産党の
第16期中央委員会第5回全体会議
(16期5中全会)のコミュニケでは、
六つの「しなければならない」事項と
七つの行動計画、
つまり、六つのPlan(方針)と
七つのDo(行動計画)があり、
それらが大筋で対応しているものの、
数の違いなどから若干変則的になっていることを
前回までにお話しました。
Planとしては上位にあるのに、
Doとしては下位に序せられているものとして、
「Plan4.都市部と農村部の協調的な発展を
促進しなければならない」
「Do6.都市部と農村部の住民の収入水準と
生活の質を向上させ、
価格水準の基本的安定を保ち、
居住、交通、教育、
文化、衛生、環境などの方面の条件を大幅に改善する」
というものがあります。
この項目は明らかに
都市部より農村部にその比重が置かれています。
それはまた後で説明しますが、
農村、農業、農民の補助育成、
いわゆる「三農」政策を
今後も注力していくことを
示しているといえるでしょう。
また、一つのPlanに二つのDoがあるものがあります。
「Plan5.調和が取れた社会建設を強化しなければならない」
「Do5.9年義務教育を普及して徹底し、
都市部の雇用機会を増加させ、
社会保障システムを健全化させ、
貧困人口を減少させ続ける」
「Do7.民主法制建設と精神文明建設に新たな進展を促し、
社会治安と生産の安全性をより好転させ、
調和の取れた社会の構築に新たな進歩を勝ち得る」がそれです。
以前、「調和が取れた(中国語:「和諧」)」が
今回のコミュニケの本当の大きなポイントだと指摘しましたが、
二つのDoが設定されているところからも、
このPlanの重要性はうかがえます。
日本でも、中国の貧富の格差が深刻化、
政権の崩壊につながる可能性が指摘されますが、
中国共産党や中国政府が、
そうしたものも含めた社会矛盾全般を解決し、
「調和が取れた社会」を作り上げていくことに、
いかに熱心かがうかがえます。
|