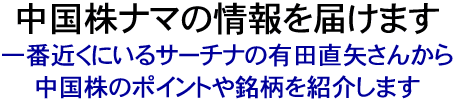|
第247回
投資と消費のアンバランス、低迷する所得の伸び
GDPを構成する重要な指標である、
投資(固定資産投資)と消費は、
中国全体で、2004年それぞれ7.7兆元と5.4兆元程度です。
日本では、
「GDPの6割が個人消費(だからこそ個人消費が重要だ)」
というのが定論ですが、
中国では逆に投資が消費を上回っています。
伸び幅でみてみても、
投資が前年比25.8%増であったのに対して、
消費は10.2%増です。
消費の伸び幅が経済成長率全体を上回ったこともあって、
「消費も堅調」と表現されますが、
投資の伸び幅はさらに大きく、
「投資は過熱」というのも事実でしょう。
この過熱を抑えるためのマクロ調整も、
やはり05年においても継続されそうです。
投資と消費を見比べたときに、
実額でも、伸び幅でも、
消費よりも投資のほうが
圧倒的に高い水準になっているのは、
決して正常といえるものではないでしょう。
「中国バブル論」は日本でも依然として盛んですが、
こうした数値は、
それを裏付ける材料の一つにもなっています。
ただ、中国は経済の高度成長期であることは間違いなく、
その分、各種インフラ整備が急務で、
それだけ、投資が増えるという現象そのものは
正常であります。
要は、程度の問題でしょう。
中国が、日本のように
消費が投資を実額で上回るということになるのは
まだまだ先のことかもしれませんが、
少なくとも、早い段階で、
消費と投資のそれぞれの伸び幅の逆転は求められます。
投資の過剰な成長を押さえるために、
今後も引き締め策は
ある程度継続されなければなりません。
と同時に、消費のさらなる成長を引き出さなければなりません。
ただ、前者は、行政的な手法を含めて、可能性は高いですが、
後者は、なかなか難しい問題を抱えています。
というのも、中国都市部の可処分所得ですが、
04年の伸び幅はわずかに実質7.7%です。
経済成長が実質9.5%という時代に、
国民の所得が、
その伸び幅に追いついていないというのが、
中国の抱える根本的な問題を象徴しているのですが、
所得が伸び悩む中で、
消費が爆発的に成長する可能性が小さいのは
いうまでもありません。
|