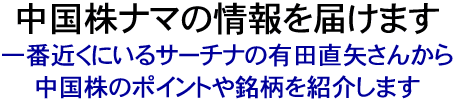|
第189回
インフレ圧力軽減につながるか? 過熱経済の抑制も
中国が9年ぶりとなる利上げが
10月28日の引け後に発表され、
29日から実施されることになりました。
H株指数は、28日の終値が4578.58ポイントでしたが、
翌29日には
一時4500ポイントを割り込む場面もありましたが、
4504.78ポイントで引けました。
しかし、週末をはさんで11月1日は一段と下げて
終値は4499.24ポイントとなりました。
この日が底となって、
11月3日には4600ポイントまで回復しましたが、
H株の「利上げショック」もB株同様、
大きなものがありました。
利上げの背景としては、やはり、
一つにはCPI(消費者物価指数)の上昇が深刻で、
インフレ圧力が強まったことが挙げられるでしょう。
中国では、「3%を超える上昇幅となれば、
インフレ傾向にあると判断できる」と、
昨年から言われてきました。
しかし、2004年2月に発表された
同年1月のCPIは
前年同月比で3.2%の上昇を記録したのです。
2月のCPIは2%台の上昇にとどまりましたが、
3月と4月は2カ月連続で3%台となり、
5月には4.4%となりました。
さらに6月には5%の大台を超え、
以降、9月までの4カ月間、5%台で推移しています。
単純に考えれば、ここ4カ月間、
中国の物価は平均して日本の消費税並みに
値上がったことを意味します。
デフレ時代の今の日本では、
CPIもマイナス成長となっており、
なかなか実感がわかないかもしれませんが、
いくら高度成長を続けているとはいえ、
これほど急激な物価上昇は、
市民生活にも大きな影響を与えることになります。
ただし、利上げに踏み切った、
しかも急ぐように実施したのは、
さらに大局的に、
中国政府が進める投資過熱抑制政策が
思うように効果を上げ切れていないことに対する
苛立ちを示しているのかもしれません。
中国のGDP(国内総生産)の成長率は、
今年1−3月で9.8%、4−6月で9.6%、
7−9月で9.1%と推移しており、
過熱気味の経済成長は徐々に落ち込んできていますが、
それでもいずれも9%台という高水準となっています。
|