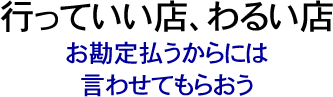|
第828回
ワインの諸々 82
ビオワインと微発泡の関係について
第807回で取り上げた「微発泡ワイン」について
色々ご意見、ご指摘をいただきましたので、
ここにまとめてみたいと思います。
1、友里はビオワインを否定するのか、嫌いなのか。
ビオワインは玉石混交でありまして、
あのインポーター関係者の煽りを真に受けなければ、
ビオの中にはおいしいものもあるでしょうが、
駄目なものも結構あるはず。
私はすべてを否定をしませんが、熟成に耐えうるワインでない、
よって熟成によるワインの真髄を味わうことのできないワイン
と申しております。
早飲みでは
それなりにおいしいワインに何回か当たった経験があります。
2、ビオワインになぜ微発泡が多いのか。
ビオには以前書きましたように2種ありまして、
減農、有機栽培などのほか、
月の満ち欠けや牛の角の入れた牛糞をまくオカルトチックな手法と
その方向性はちょっと違うようですが、
そのビオと微発泡は必ずしもイコールではないようです。
酸化防止剤である、SO2を
醸造過程や瓶詰めの段階で入れたがらない造り手が多いからか、
結果として微発泡ワインが多いということのようです。
SO2をなぜだか入れたくない、
しかしそうすると酸化してワインが駄目になりやすい、
ではどうするかというと、醸造過程でCO2の雰囲気をそのまま残し、
瓶詰めの際も完全にCO2を除去しない。
よって、抜栓時、舌先にチリチリ感ある
微発泡ワインが誕生してしまうのではないかとのことでした。
敢えて誤解を覚悟で言わしていただければ、
ビオの造り手がSO2を嫌い、CO2の助けで酸化を防いでいるのは
本末転倒ではないかと。
本当にSO2が体に悪いとしても、
CO2の助けでわざわざ味の悪いワインを造る必要があるのか。
本当に体を気にするならワインを飲まなければいいわけです。
高脂血症などの人が、フォアグラを避けているように、
気になるならとらなければいい。
売上が鈍ってくると
どうしても目先の変わった品物を生産して
売上を戻したくなるのが人情です。
今までの古典的手法のワインの販売が伸び悩む中、
古典的ワイン=悪、すなわちSO2=悪 のレッテルをはり、
ビオ=体に良い との錯覚を与えて
新しい客層をも取り組む業界の狙いがそこにあると考えます。
そして最近また、日本ワインが大きく取り上げられています。
熟成に耐えうるワインが出来ないと考える(個人的な意見ですが)
日本ワインが売上を伸ばすには、
熟成ワインを否定してビオに奔らざるを得ないのでしょうか。
またまた言い過ぎだとお叱りを受けるかもしれません。
|