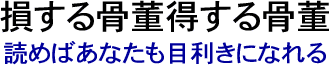|
第38回
商品学(中国陶磁編)
5.海を渡った唐三彩の話 戸板山盛りの骨董品
中は30平米くらいの部屋だった。
別に骨董品が飾ってあるわけではなく
部屋の中央に大きなテーブルがドンと置いてあった。
その周囲に椅子が4脚あった。
僕たちはめいめい椅子に座った。
お茶を運んでくるわけでもなく、
通訳が状況を説明するのでもなく、しばらく空虚な時間が流れた。
案内してくれた店主は奥に消えたが、
しばらくして手伝いみたいな人と一緒に入ってきた。
彼らは戸板のようなところに
皿や鉢、壷や人形をごちゃごちゃと積み上げて運んできた。
そして3人がかりで中央のテーブルの上にそっと置いた。
僕のほうを見て店主が
「この台の上のもの必要ですか?」と問いかけてきた。
「必要ですか」といわれても
積み上げられたものは大よそ5、60点もありチェックもできない。
それに時代もバラバラで傷の有無も分からない状態だから
返事の仕様がなかった。
「ちょっとチェックさせてください。」
といって壷や鉢を取り上げルーペで見ていると
手伝いの二人が戸板を持ち上げて向こうへ持っていってしまった。
「ああ、ちょっとまって。」といっても
「まだありますから」といいながら
先程の手伝いが同じような戸板に乗せた作品を山盛りで運んできた。
2回目の戸板の上には5、60点の唐三彩の人形が乗っていた。
15、6センチくらいの婦人俑や文官俑だったが、
駱駝や馬の様な大物はなかった。
人形は首が折れたり下の部分が壊れたりしていたが
日本のマーケットでは結構良い値で売れると思った。
(昨今のマーケットだったら値段も付かないが
何しろ当時は中国陶磁がとても高価な時代だった。)
婦人俑のうち一つを取り上げて
これは幾らですかと尋ねると、
戸板の上に乗っているもの全部で1000万というのだ。
一つずつ積み上げて計算すると
1000万くらいは十分価値があると思ったが、
60〜70%のものはクオリティが悪く扱えないようなものだった。
もたもたしていると
その戸板を手伝いがまた奥のほうへ持っていってしまった。
そのときになって僕はここのシステムがなんとなく分かってきた。
戸板の上の作品を一括で買えといっているのだ。
しかもこれは政府の売り物ではなくて
どこかからもってきたものを販売し、
その売上を中国共産党青年同盟が
コミッションをもらう仕掛けかと思った。
横にいた通訳に
「ここで買っても持ち出しできるんだろうね。」と念を押すと
「大丈夫です。証明書もつけますから」ということなので
次の戸板は買い逃さないようしっかり見ようと思った。
3度目の戸板が運ばれてきたがこれは銅器だった。
銅剣や、鏡、小さな鼎のようなものがやはり6、70個乗っていた。
これは重かったのか手伝いもかなりしんどそうにしていたし、
板もしなっていた。
中の銅剣を取りあげてみると
柄の辺りに学術的な発掘時につける
ナンバーのようなものが付いていた。
「う〜ん。」
といって考えているうちまた持っていかれてしまった。
「先生、これで終わりです」
まだ戸板がどんどん出てくるのかと思っていたら
そこで終わりだという。
「それじゃはじめの戸板をもう一度みたい」
というと店主が意地悪そうな顔をして
「だめですワ。」と冷たく言い放った。
商売をする気がまったくなく
どこかの国の官僚的なやり口によく似ていた。
それにしてもこの時点で感じたことがあった。
きっと近いうち
中国の骨董品が世界のマーケットにあふれるだろう。
唐三彩も北宋の白磁も春秋戦国の銅器も
ガタガタに値段が下がるのではないかと思った。
「先生、封建領主たちが人民の尊い汗と血を持って作った
これらのものを人民が今暴いてここに並べてあるのです。
しかし先生はどれも興味を示されなかったのでおわります」
といってすべてがジエンドとなった。
|