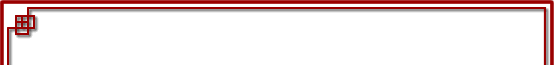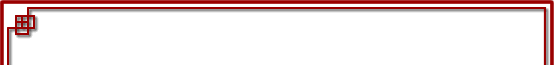荘子は生まれながらに亡国の氏としての辛酸をなめたため、ああした消極的退嬰的な、見方によっては狡猾な、思想をもつようになったらしいという荘子観が日本にはあるようである。荘子の哲学が弱者の哲学としての一面をもっていることは事実であるが、狡滑、であることをただちに植民地的と結びつけることは果たして妥当であろうか。ことにその出身地と結びつけて、吉田茂は土佐的であるとか、岸信介は長州的であるとかいった出身地別の人物評価は、日本人にはわかりがよいかもしれないか、年来、私はこうした戸籍調査官的方法には疑問をいだいている。狡滑であることは環境と関係があるにきまっているけれども、おそらくそれ以上に、鋭い頭の働きと関係があるように私には思われるからである。したがって、荘子の思想は、私には荘子の才能のすべてであるよりは、才能のおつりのように受け取れるのである。
私が『荘子』を着物の裏地にたとえたもう一つの理由は、老荘思想と一見対立的な立場にある孔孟思想を私が念頭においているからである。なるほど荘子は徹頭徹尾、孔子を攻撃したり、揶揄したりして、まるで仇敵に対するごとき観があるけれども、この二つの思想はお互いにまったく相容れない存在ではない。ちょうど、カトリックとプロテスタントが犬猿のごとき仲でありながら、「キリスト」という一点で一致しているように、孔孟の儒家と老荘の道家は「人間」という一点ではまったく一致している。ともに人間中心の考え方であるがゆえに、現世しか問題にしないが、その生き方については意見が分かれ、その場合、きわめて顕著な事実は、荘子のほうが酒を飲んだ批評家のように、しきりに孔子にからんでいることである。これは着物の裏地が表地に喧嘩を売っているようなもので、孔孟の側がたいして相手にしようとしないのは、現に表地として世間に通用しているなによりの証拠であろう。
そうして、着物を着るわれわれ人間の立場からすれば、裏も表も同時に着ているのがふつうである。ことばをかえていえば、この二つの思想は近ごろよく見かける両面用のコートのごとく、雨が降りだせば、ただちにひっくり返してレインコートとして使用できる性質のものである。さきに私は同じ米から作られた飯と酒の関係に擬したが、実際、われわれが自ら顧みて、自分のなかにこの二つのものが同時にいくらかずつの割合で存在していることを感ずる。たわいのない話だが、出世街道を一路順風で進んでいるときはまず天下国家も胸三寸のなかと思っている人でも、気勢があがらなくなったときや、隠退を強いられて急に老い込んでくると、とたんに老荘の「莫逆の友」になるというはなはだ身勝手な傾向がある。老荘思想はそんなときの、われわれにとって「駆込み寺」のような役割を果たしている。
この意味で、老荘思想は孔孟思想に比べて、より年をとっているように私には思われる。
もっとも、年をとっているというのは、老荘思想のほうが先に生まれたということではなくて、一人の人間が年をとってから身につけるという意味であるから、時代的にいえば、より後期になる。ところが、年をとってから身につけた思想のほうが権威があるように人間は錯覚しがちであるから、ゆきがかり上、どうしても老荘思想のほうがオヤジであるような話を作り出さなければ引っ込みがつかなくなった。
『史記』のなかで司馬遷も、孔子が老子から教えを受けたような記述をしているが、私は実在人物としての老子の存在を疑っている。中国人が喧嘩をするときに、自分のほうが目上だぞという意味で、よく自分のことを你老爸(ニイロウバ)などと称するところをみると、本家争いをしているうちにおれのほうがオヤジだ、という意味で、いつのまにか老子のほうが年代的に先だということになったのではなかろうか。
その点、荘子が孔子より年代的にあとであることは、荘子が孔子を自分の作中に登場させて思いのままに動かしたり、からかったりしている事実からも明らかである。そして、孔子が終始一貴リアリストとしての一生を終えたのに比して、荘子は行動し思索する自分に一定の距離をおき、人生を一種の遊びと見なすことによって自分自身をさえ戯画化しようとした。
『荘子』三十三篇をしいたげられた弱者の狡猾な処世哲学として見るよりも、常識豊富にして有能なる男が「才能のつり銭」をもてあましているのだと見るほうが、荘子の面目をいっそう躍如とさせるのではあるまいか。 |