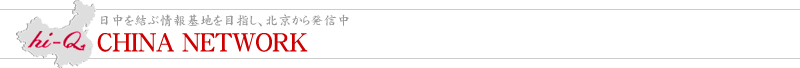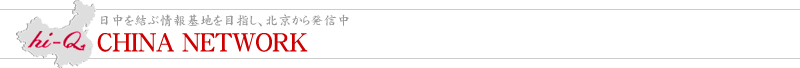|
会社の利益率について邱先生よりダメ出しをされた私は、また猛烈に考え始めました。
売上があがってきて一安心していたところに
事業の根本的な問題点を指摘されたからです。
「客観的に見ると今売上は上がってきているものの利益率が異常に低い。
50人の従業員(現在は150名ほど)を抱え、
自分自身つらい思いをしてそれで利益がこれっぽっちじゃ、誰だって面白くない。
利益率、絶対高めなきゃだめだな。」
当時、私の中にあった1つの考えは、
「この事業は必ず大きくなるだろう。
それならば、最初の1店舗から多店舗管理ができる組織作りをしよう。
あえて、店舗と本部をつくろう。」というものでした。
最初から負担の大きい、費用のかかる組織構造だったわけです。
こう考えたのは・・・たとえばスターバックスコーヒーの発展の歴史を見ると、
1990年代以降急速な発展を遂げたスターバックスですが、
87年からの3年間は莫大な赤字を出しているのです。
その当時、ハワード・シュルツが社内外に繰り返し発していたメッセージが
「将来を見通し、先行投資をしなければならない。」
というものでした。
正直に告白すると、当時の自社の損失を私は
"将来に対する投資だ"と誤解していたのでした。
しかし、目が覚めたのは先生の「それだけしか儲からないの?」という強烈なパンチと、
もうひとつは、ユニクロの柳井さんが
「プロフェッショナル・マネージャー」という本の中で語っている
ロンドン出店の失敗を分析した次の文でした。
「失敗の原因は、"3年間で50店舗"という言葉が独り歩きし、
まず1店舗から儲けを出すことを基本に、
儲かる仕組みを徐々に拡大するという基本を怠ったことにある。」
「やっぱりそうだよな。規模の経済なんていっちゃって、
単に今儲かってないことの言い訳をすべきではないない。」と考えを改めたのでした。
私はそこで改めて師匠の知恵を借りることにしました。
といっても邱先生に電話をして聞くというわけではありません。
"邱永漢的良い事業"とはなんだろうか?ということについて勉強をはじめました。
時に、私にとってのよき教科書とはこの9393のHPです。
私は邱先生の過去のコラムを全て見返すことにしました。
過去の「ほぼ日刊いとい新聞」時代を含めてですから、数年間さかのぼることになります。
(ちなみに、私はこの作業をするのは2回目です。1回目は先生とはじめて会う前でした)
勉強の結果"邱永漢的よい事業"を次のように私なりに定義しました。
1) そもそも事業の利益率が高いこと
2) 売上の拡大にしたがって、利益が"加速的に"増加すること
3) 投資回収期間が短いこと
この3つの指針を今一度自分の頭にしっかりと刻みつけ、
自分の頬をぴしぴしと叩き、気合を入れなおしたのでした。
「よし必ず儲けるぞ!」
|