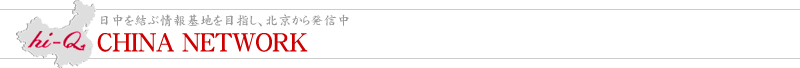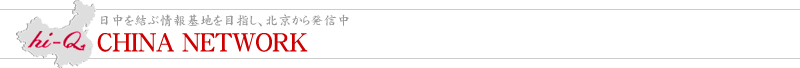|
おばあちゃん自慢のタレをあきらめた話をしましたが、
事業を営む上でつくづく思うのは、「事業というのは市場との対話」であるということです。
先生が言うところの"経営は心理学"であるということです。
市場、消費者、従業員といった人間の心を理解し、相手にあわせて1つ1つ手を打つ。
その過程で、相手の好きなもの、嫌いなものを判別し、
また最高のタイミングと距離感でそれを提供していく。
松下幸之助さんは経営は芸術といいましたが、まさしくその通りだと思います。
そう、人間をよく観察し、心を理解する必要があるのです。
ところで、邱先生は人を理解するときによくご自宅で食事を振舞っていらっしゃいます。
食事を通して、相手の人間性を感じとっていらっしゃるのだと思います。
以下は私の理解であり、また極端な見方ではありますが、
邱先生との食事を通して、
「食事とは人間理解のうえで極めて多くの要素が含まれているものだな。」と感じています。
まずは、食前の会話から始まります。
相手の健康状態やおなかの具合等をさりげなく理解するのはこのタイミングです。
そして、テーブルに着くにあたっては、ホスト(ご主人)の位置、
そしてホストの意向を汲み取りながら、テーブルに近づくタイミング、
そしてホストの視線からどこに座るべきかを感じ取る。
スタートした後は、一品一品をいただく順番。
いい忘れましたが、邱先生のご自宅は中華テーブルで、
いわゆるクルーっと回るあのテーブルです。
また食事のスタイルは、日本式に一人ひとり分けられているのではなく、
これまた中国式に、ひとつのお皿に盛られて出てきます。
このクルーっとまわすタイミングと、
皿に取り分けていただくタイミングや量がとても難しいのです。
食事中は、全体の雰囲気を感じながら、お酒や乾杯のタイミング、
また他の参加者の方が好きなものがあれば、
それを食べやすいようにテーブルをまわしたりと、考えることは多いものです。
まあ、考えすぎるとせっかくの味がわからなくなるのでやりすぎは禁物ですが。
ここまで書いて、「あー日本の茶道と一緒だな。」と思い出しました。
私は、東京に住んでいるときに茶道を数年間習っていましたが、
相手に対する気遣いを言葉ではなく、形で表現していくことが
茶道の本質だったと理解していました。
なんでも一緒なんですね。
一言でいうと"気遣い"ですが。これが事業をやるうえでの肝といえば肝です。
こんな風に書いて楽しい食事を小難しいものに仕立て上げると、
「キムくんうんちく言ってないでおいしくきれいに平らげればいいの。」
と先生に一言叱られそうですが・・・。
|