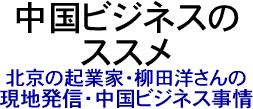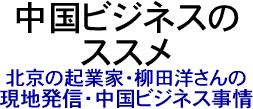|
第1530回
残念な中国の生ビール
生ビールがおいしい季節となってまいりました。
レストランに入ったら
「とりあえず生一つ!」といきたいところなのですが、
私は北京ではほとんど生ビールを飲みません。
なぜなら、北京では残念な生ビールが出てくる確率が
高すぎるからです。
残念な生ビールとは、冷えていない、炭酸が弱い、
泡がない、逆に半分近くが泡、
そして、ひどいときには酸っぱい味がする、
などの生ビールです。
こうした生ビールが出てくると、
とりあえずは店員にクレームをするのですが、
「生ビールは本来どうあるべきか」
というイメージをまったく持っていない彼らに
私の悔しさが伝わるわけもなく、
結局は瓶ビールにかえてもらうことになります。
このやり取りが面倒なため、私は最近は専ら、
最初から瓶ビールを頼むようになってしまいました。
どうして、北京では残念な生ビールが多いのか?
それは、生ビールは生産者であるビール工場よりも、
末端にいる生ビールを注ぐレストランの店員のほうが、
その生ビールの質に影響を与える度合いが
強い商品だからだと思われます。
いくらビール工場が品質のよいおいしいビールを出荷しても、
レストランの店員がビールサーバーの洗浄を怠ったり、
温度や炭酸圧の設定を間違えたり、
注ぎ方がなっていなかったりするだけで、
その生ビールは台無しになってしまうのです。
その点、瓶ビールはビール工場が
きちんとした品質のものを出荷さえすれば、
レストラン側がその品質に
影響を与えることはあまりありません。
あったとしても、残念な思いをするのは
「当店には常温のビールしかございません」
と言われたときぐらいで、
少なくとも酸っぱいビールを
飲まされるような心配はありません。
中国では生ビールに限らず、
末端の店員の技量に頼るような商品を
販売することには無理があります。
なぜなら、せっかく品質のよい商品を提供しても、
末端の店員がそれを台無しにしてしまう可能性が
大きいからです。
中国でモノを売る場合には、瓶ビールのように、
品質は工場を出た時点で既にほぼ確定しており、
末端の店員はその商品をお客さんに渡して、
おカネを受け取るだけ、というようなモノに
したほうがよいのではないかと思います。
|