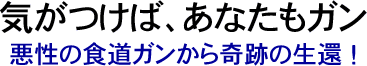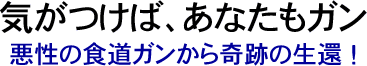|
第1652回
「いのちの手帖」の巻頭言
『ラジオ深夜便』3月号にも収録された
帯津医師の演題は「輝け!熟年『ドキドキしていますか?
〜私のときめき養生法』 」について前回ふれました。
――帯津さんご自身は、どんなことでドキドキしますか。
帯津 最近では、「夏目漱石について書け」という
原稿依頼がきたことです。(略)
と、そのインタビュー記事で話しておられますが。
3月10日発売の「いのちの手帖」第3号・
春夏特大号の帯津良一博士による巻頭言の演題も
「文豪・夏目漱石の死生観」です。
若い日の医学生の思い出の数々を逍遥し、
漱石の名作『野分』から希望の死生観を探り出すという内容で、
「心のトキメキ」日々の果てに開ける、
悔いなき人生の旅路について書き綴っております。
さわりを紹介しましょう。
*
医学部に進学したのが1957年。
そこには夏目漱石の「三四郎」の世界が開かれていた。
まずは本郷三丁目の交叉点。
思い出すのは
真夏の陽光の下に静まり返る交叉点だ。
夏休みになって学生が居なくなって人通りは絶え、
動いているのは都電だけ。
真砂町の方から見て、左手前が交番、
その頃は長い顎鬚(あごひげ)のお巡りさんが立っていた。
右手前は小間物屋、有名な「本郷もかねやすまでは江戸の内」
とうたわれた「かねやす」である。
三四郎の郷里の先輩である野々宮宗八さんが、
誰に贈るのか、ヘリオトロープなる香水を買うのが、
このかねやすだ。
右手の奥は『三原堂』と『藤村』という
和菓子屋が二軒並んでいる。
なぜ並んでいるのか誰かに訊いたことはない。
そして左手の奥が小さなレストラン。
不思議なことに屋号の記憶はない。
いつも白地の小さなのれんがはためいていた。
小振りな海老フライが一つと、
これまた小振りなハンバーグが一つ、
キャベツに俵型のご飯が一つの皿に盛られている定食が好きで、
この店によく入った。
いつも一人である。
食べながら、どういうわけか、いつも三四郎の気分だった。
広田先生の入る青木堂なるレストランが
どのあたりにあったのかわからないが、
本郷通りの白十字とか
少し奥に入った天神山などにその気配を感じていた。
もちろん、まだ見ぬ里見美禰子(さとみみねこ)には
大いに関心を抱いていて、
三四郎池の附近や真砂町界隈を歩く時は、
いつもその面影を求めていた。
三四郎の世界はそんなだったから死には縁がない。
死について考えるようになるのは、かなり後のことである。
もっとも解剖実習で死体と対峙し、
その頃、芥川賞にかがやいた大江健三郎さんの
『死者の奢り(おごり)』を読んでも、
相手はあくまでも死体であって、
死そのものではないである。
いつの頃からか、死ぬときはがんがいいと思うようになった。
がんなら、脳卒中や心筋梗塞と違って、
死ぬ前に時間的余裕があるので、
自分の一生を顧みて、
これを総括できると思ったからである。(略)
*
ホリスティック医学の魁(さきがけ)である、
帯津医師の「養生法の深奥」を知りたい人は、
まずこの巻頭言から、
新発売「いのちの手帖」3月号をお読み下さい。
|