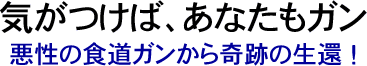|
第1085回
続・安岡章太郎著「観自在」を読む
作家の安岡章太郎さんから送られてきた
近著「観自在」(世界文化社)の
感想の話の続きです。
この本、タイトルは「観自在」ですが、
別に宗教臭い作品ではなく、
安岡さんらしく、
気ままに自在に生きてきた人生観――、
「ものの見方・考え方」を説いた
49篇を収録した軽妙な随筆集なのです。
ちなみに観自在とは?
「観世音菩薩」(かんぜおんぼさつ)、
もしくは「観自在菩薩」(かんじざいぼさつ)と呼ばれ、
一切の人々を観察して、
その苦を救うのが自在な菩薩のことですが、
このエッセイ集では
「人生は、観い(おもい)のままに、自由自在であれ」
といった意味なのでしょう。
というわけで、
中でも歴史に対する考察が痛烈です。
「世界史としてのアジア」というエッセイなどには、
まさに安岡流の「自由自在思考のすすめ」が
存分に展開されております。
「世界史を理解するための鍵は
東洋に匿(かくれ)ているのではないだろうか」
「すべて研究は竹の根のように(略)
新しい芽を出すべきものである」と主張する
「宮崎市定 アジア史論考」を
とりあげて共鳴しています。
「歴史に限らず学問と名のついたものは(略)、
学者によって《荘園化》されていることか]と批判し、
「なんでも見てやろう」式の
自在な歴史視点の大切さを説いています。
たとえば
「明治維新のとき、
薩摩と長州が最も強く攘夷を主張したが、
これは薩長二藩が
当時密貿易で莫大な利益を上げており、
鎖国を解いて開港すれば
密貿易の利益が得られなくなるからである」
とする、宮崎市定・独特の
「幕末論」と自在史観を取り上げています。
安岡章太郎ファンなら、
幕末から明治維新までの歴史と運命を描いた
『流離譚』や『鏡川』という名作や、
「ドン・キホーテと軍神」といった名エッセイを
読んだことがあるでしょうが、
「とらわれない目」をいつも大切にしてきた
安岡さんの作品の原点がわかる論考です。
というわけで、
この本の最後に収録されたエッセイが印象的です。
「しかし今日余りにもどうでもいいような本が
氾濫しすぎているのではないか」と、
最近の出版傾向についても皮肉を込めて綴っておられます。
“なにごとも、心が縛られていては、
真の観自在は実現できない“というわけです。
ともすれば、“とらわれやすい”
この時代に向けられた
軽妙にして痛烈な随想集ですから、
夏休みに必読の一冊として、奨めておきます。
|