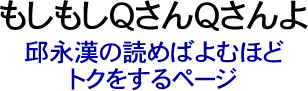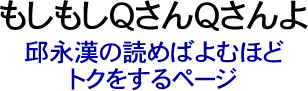|
第200回
邱飯店は一げんさんは入れません
私は食べることにうるさい家に育ちました。
私の生家では毎日、
夕食をするのに2時間もかかりました。
毎日がフルコースですから、
子供は親の相手なんかしておられませんよね。
自分たちだけさっさとおかずとめしをかきこんで
腹一杯になったら、すぐ食膳を離れます。
うちの父親は酒飲みでしたから、
それからでもまだゆっくり酒を飲み続けています。
小学校に入って昼飯時に
クラスメートの弁当の中を覗き込むまでは、
自分の家の食事がそんなに賑やかなものであることを
知りませんでした。
冷飯は牢屋に入った時に食べるものだと
台湾の人たちは考えていましたから、
私の弁当は毎日、家の使用人がわざわざ自転車で
ほかほかと熱いのを小学校まで届けてくれました。
私の弁当は重箱の半分がご飯で、半分はおかずでした。
友達の弁当を見ると、アルミの弁当箱の片隅に
小さなおかずの容れものがあって、
その中にちょっと載っているだけでした。
私の弁当の中身を覗き込んだ友達はとても驚き、
とても羨ましがりました。
仲好くなった友達は午前中だけで授業の終った日は
私が誘うとすぐ私について私の家に食事をしに来ました。
おいしいおいしいと言って
骨まで噛みくだいて食べるのを見て、
私は人をご馳走する楽しみを覚えました。
私は人をご馳走することを
人生の楽しみの一つと思っています。
東京に住むようになってからも、
よく人を家に招き、最初の頃は
私が築地や横浜の中華街まで買い出しに行き、
家内がコックをつとめてもてなしました。
のちにプロの中華料理のコックをやとい、
文人墨客から産業界の名士まで
我が家の常連になりましたので、
「おい、邱飯店にメシを食いに行こうや」
という人も現われました。
我が家の料理に「邱飯店」と名をつけたのは
文芸春秋の名編集長でのちに社長をつとめた
池島信平さんでした。
でも邱飯店は一げんさんは入れてくれないし、
お勘定をとらないので、
誰でもというわけには行かないという欠点があります。
|