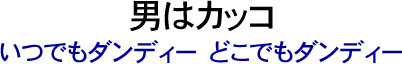|
第233回
俳句を詠んでみませんか(1)
俳句上達法を知っていますか。
それは実に簡単なことで、
季寄せ、歳時記のたぐいを開いてみる。
いろいろな句が並んでいますし、
また、どんな季語があるかも分ります。
なかにはいったい何が言いたいのか、
さっぱり分らない句もあります。
その一方で、必ずひとつやふたつ好きな句を発見するでしょう。
最初はこれを真似るつもりでやってみれば良いのです。
若葉して御目の雫ぬぐはばや(芭蕉)
これは芭蕉が奈良に行き、唐招提寺、鑑真和尚を拝した時の句。
鑑真は天平時代の高僧ですから、
芭蕉の時代から眺めてもざっと1000年近い距離があります。
けれどもその1000年をすっと超えて、
「あなた様の涙をふいて差上げたいなあ」と言っているわけです。
だいたい涙が出ていると思うのも、芭蕉の勝手な想像でしょう。
一言でいえば超現実的な句です。
けれども芭蕉がそこでいかに感動したか、
ということは伝わってきます。
ちょうど名人の手品を見るような鮮さがあります。
季語は若葉(夏)で、
御堂のなかの暗さとコントラストも活きています―
といったふうに考えていると、
なにかを見る時の観察力が違ってくるでしょう。
私なども初夏の頃に奈良に行ってみたい。
鑑真像を拝見してみたいと思う。
これで旅の理由がひとつ出来るわけですから、
これもひとつの効用でしょう。
それはともかく好きな句を発見して、
どうしてその句が好きなのかをじっくり考えるようにすると、
絶対に俳句は上達します。
でも、ここで問題なのは、
あまり上達しすぎるのも困ったものです。
趣味のはずが趣味でなくなってしまうから。
趣味ではじめたゴルフで、
突然先生になってしまうようなものです。
芭蕉もこんなに上手にならず、
適当にやっておけばもっと永生きしたと思います。
これとは関係ないことですが、
昭和期の俳人はたいてい永生きです。
私は俳句に遊ぶことは、
なによりの永生きの秘訣だと思っています。
|