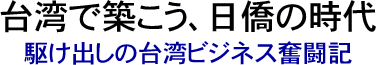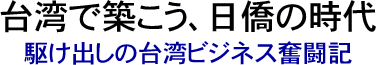|
第144回
音楽配信サービス/何が消費者にとって良いのか
待ちにまったアップルの楽曲ダウンロードサービスが始まりました!
と言っても、日本の話で、台湾ではまだですが・・・。
100万曲以上のレパートリーを揃え、
1曲のダウンロード価格が150円と他社サービスの約半額で、
サービス開始後4日間で販売数が
これまた100万曲超(16日間で200万曲突破)、と
上々の滑り出しのようです。
2年前にスタートした本国アメリカでは
既にダウンロード数が5億曲を超え、
価格も99セントと「1曲ワンコイン」が実現済、
アップルは業界70%のシェアを維持していると言われています。
日本での導入が遅れたのは、
「複雑な著作権問題」が原因とのことで、
ソニーミュージックエンターテインメント(SME)は
参加を見合わせています。
今から6年ほど前に、
アメリカで「ナップスター」という
音楽共有のソフトが若者の間で大流行しました。
インターネットを介して、
他人が持っている楽曲をタダで自由にコピー、
共有できるという画期的なソフトですが、
全米レコード協会に訴えられ、
2002年には一旦消滅してしまいました。
ただし、デジタル化した音楽は簡単にコピーができ
世界中に広がってしまう、という事実は残りました。
誰もがタダで音楽をコピーするようになったら、
音楽をビジネスにする人はいなくなるのか?
消費者を、「この値段でこんなに便利なら買ってもいい」
という気持ちにさせたのがアップルでした。
自分の買いたい曲だけ買える、
パソコンがインターネットにつながっていれば
24時間いつでもどこでも買える、
コピーもある程度認められる、
ソフトがとても使いやすい、
iPodにコピーすれば気軽に持ち歩ける・・・。
これほど便利なら買います、よね?
利益を上げるために、
自分たちのやり方、あるいは考え方を守りたい、
今までそれで成功してきたなら尚更です。
しかし、商品やサービスを
使ってもらうお客様に喜んでもらえなければ、
やがてそっぽを向かれてしまいます。
今のところ参加を見合わせているSME(ソニー)が、
ハードに拘らず、果たして態度を変えるのか、注目しています。
|