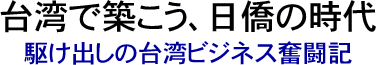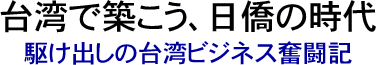|
第125回
カラオケ・イン台湾
台湾の人たちは、総じて唄が好きなように思われます。
このあいだの台風「海棠(はいたん)」では、
台北市内の被害は予想されたほどにはひどくなかったのですが、
風雨が少し止んだ途端にKTV(カラオケボックス)に繰り出し、
家族ぐるみ、あるいは友達同士で熱唱する姿が
TVニュースで放映されていました。
恐るべし、台湾人。
唱の好みは当然年代やヒトによりバラバラですが、
高年齢層はやはり浪花節系
(北京語で何と言ったらいいのかわかりません)がよいみたいです。
70歳台以上であれば日本語がわかるはずですが、
戦後生まれで日本語がしゃべれなくても演歌は好きみたいで、
バスに乗ると時々、北島三郎とか、五木ひろしとか、
大音量でかかっていたりします。
タクシーに乗っても、
客が日本人だとわかると気をきかしたつもりで
日本の楽曲をかけてくれる運転手さんがいますが、
いったいいつの、誰の唱なのか皆目見当つかなかったりするところが
ご愛嬌です。
若い人たちの間では、もちろんラップとかポップスとか、
そういうジャンルですが、
他のアジア諸国同様、
日本人歌手には親しみを感じてもらっているみたいです。
「宇多田(ゆーどぅおーてぃえん)」とか
「濱崎歩(びんちーぶー)」とか、
最近では「Orange Range(これはそのまま)」
とかですね。
台湾の歌手でも、北京語+英語のポップス系で
米系や日系のアーティストを追っかけている歌手もあれば、
台湾語にこだわる長渕剛系のシンガーもおり多種多彩です。
カラオケではバラード系の唄が好んで唄われるので、
日本人がこれらの唄を覚えて披露すると、仲間に入れてもらえます。
一緒に楽しんでいて面白いのは、
唄う部分が終わるとさっさとちょん切って、
次の唄に入るところです。
これは映画でも同じで、
本編が終わると最後のクレジットを気にすることなく
席を立ち出口へ殺到します。
コンサートでは、
歌手が舞台を去るとアンコールなしでさっさと・・・。
余韻を楽しみたい我々にとっては「・・・」、なのですが、
これも民族性、ということでしょうか?
|