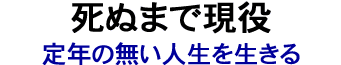|
第83回
雑巾がけ三年で責任ある仕事
当時の台湾はまだ成長経済が始まるか、
始まらないかの胎動期で、人寿保険公司(生保)とか、
投資信託公司(信託銀行)を設立して
金づるをつかんだ連中が系列企業の組織化に乗り出したところであった。
ある信託公司のオーナーは、一タ、私と会食するのに、
自分の系列会社の総経理(社長)を全部集めて一人一人、
私に紹介をした。
食事の間に、私がそれらの人々に
「あなたは以前は何をやっていましたか?」ときくと、
一人の例外もなく「××銀行の支店長をやっていました」
という返事がかえってきた。
「なるほど企業家の育っていないところでは、
一番それに近いと思われるのは、
ふだんからお金を扱いなれている銀行員なんだなあ」と私は納得したが、
同時にこういう組織ではいずれうまくいかなくなるだろうと思った。
というのは、銀行の支店長は、
お金は扱いなれているかもしれないが、
究極において企業家ではない。
そういうサラリーマンに、
メーカーや流通業のマネージメントができるわけがないのである。
はたして五年もしないうちに、一人やめ、二人やめ、
ついに一人もいなくなってしまった。
そして、本体の投資信託公司自身が倒産に追い込まれて、
とうとう人手に渡ってしまった。
私はもし新しい会社をつくってチーム・ワークでやるなら、
人材もはじめからつくらなければならないのではないかと思った。
日本の企業を見てもわかるように、
どこかから人材を引っこ抜いてきてトップに据えるようなことは、
原則としてやっていない。
平社員すら中途採用をきらい、
社会人として白紙の状態にある学校出たてを採用して、
自分たちの社風に合った教育をする。
そういうやり方をしようと思えば、
まだ世間の風に汚染されていない若者でないと駄目だろうと考えて、
私も二十四、五歳の若者を採用し、
自分の運転手や鞄持ちからやらせた。
日本でも上場会社の社長になった人には、
秘書上がりの人が多いが、
社長の秘書をやっていて社長が何を考えているかよくわかり、
社長が何をしてくれるという前に、
社長の意志通りのことができれば、社長の代わりがつとまる。
社長の側から見ていても、何百人、何千人もいる社員の中で、
一番社長に接触するチャンスが多いのだから、
どんな人物か、認められれば、それが本人の出世のきっかけになる。
ただいくらチャンスをあたえられても、
それをつかみきれない人は多い。
「こけの一念」というか、「辛抱強さ」というか、
つらいことがあっても、それに耐えることができないと
事業には成功できないものである。
だから私は「雑巾がけ」を三年やれない者には
責任のある仕事は任せないことにしている。
私の観察によれば、若い人は勤めて七カ月目に迷いが絶頂に達する。
そこで大半の者が退職をする。
そこを乗り越えた若者も、人によって違いがあるが一年目、
二年目でやめることがある。
しかし、三年すぎてもやめない若者は、
もうよほどのことがない限りやめることはない。
三年すぎてもまだいるということは、
案外職場の水によく合っているとか、
この職場で自分の人生を切りひらいて行く気のある奴と見てよいのである。
|