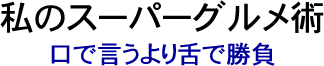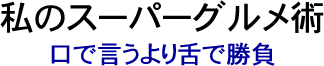|
第438回
東京湾の自然はこうして消えていった
東京湾の歴史を振返るのに、
江戸時代、明治から敗戦まで、敗戦後と
3段階にわけて考えるのが分かりやすい。
江戸の発展の出発点は長禄元年(1457年)の太田道灌の築城。
現在の皇居東御苑にあたる台地だった。
すぐ南が日比谷の入り江、すなわち海岸沿いであったという。
その後、徳川家康が江戸に府を移したのが天正18年(1590年)。
その当時は東京湾の僅か10kmの沿岸に、
渡良瀬川、利根川、荒川、綾瀬川、入間川と
5本の大河が流れ込んでいた。
そして、その河口付近の流域は広大な沖積層平野となっていて、
大雨で河川が氾濫して、荒涼たる湿地帯となって、
とても農作物をつくるような土地ではなかった。
そのために、幕府は土木工事によって、
河口の湿原地帯を数十万人の市民が生活する都市と、
広大肥沃な農耕地に作り変えることを試みた。
飲料水を得るための神田上水を設営し、
利根川と渡良瀬川を東京湾から
鹿島灘の銚子のほうに瀬変えをする治水工事を行い、
また、日比谷の入り江を埋めたてる工事を行っている。
また、東京湾へ注ぐ他の河川も何本かまとめる治水工事を進め、
江戸は周囲の穀物地帯の確保と、物資の水上輸送の可能となり、
江戸と海の関わりは深くなっている。
そして、東京湾の埋め立てはその後も続けられてきたが、
江戸時代には漁業を保護育成する考えがあり、
昭和の復興のような
めちゃくちゃな土木工事のプロジェクトが推進されたわけではない。
江戸の頃に埋め立てられた東京湾は、210haで、
これは内湾12万haのわずか0.2%だ。
そして、黒船が来て、明治維新となり、
明治から大正、昭和の初期にかけて、工業化が促進される。
1913年からは鶴見から川崎までの京浜工業地帯が作られ、
578haが埋め立てられ、
第2次世界大戦の前には軍事産業の振興のために
川崎地区が600ha埋め立てられるなど、
この期間の埋め立てた面積は3252haと、
内湾の2.8%が埋め立てられている。
戦後の10年は、
空襲による京浜工業地帯の壊滅と下町の軽工業地帯の消滅で、
垂れ流しが無くなり、東京湾の水質はよくなっている。
このときは埋め立ても268haと少ない。
ところが、戦後10年過ぎた1955年からは、
昭和の高度経済成長期になって、
2万ha以上の大規模の埋め立てによって、
漁場の多くが姿を消した。
特に、浦安から富津へかけての
千葉の京葉臨海コンビナート形成の復興計画によって、
干潟の多くが姿を消している。
干潟は幼稚魚の隠れ場になり、
アマモなどの海草や海藻によって、水中の栄養分が吸収され、
また栄養源によって多量に発生した
プランクトンが二枚貝やエビ、カニ、ゴカイなどが食べて、
海水は浄化される。
つまり、東京湾のなかで
干潟が生態系維持のための極めて重要な役割を果たしているが、
その9割が戦後の復興計画で消失し、
その頃に工業地帯が
垂れ流した有害物質を浄化する能力が無くなってしまった。
このように、戦後になって
22,9994haと東京湾内湾の19%に相当する面積が
埋め立てられてしまった。
そして、内湾の富津岬から観音崎灯台までの
海岸線の総延長686kmのうち自然の海岸は23.6kmと、
僅か3.4%しか残されていない状態になっている。
しかし、近年は東京湾の水質は改善されつつあり、
絶滅しかかっていた鮎やシャコも戻ってきている。
壊滅的なダメージを受けたが、
まだ、江戸前の美味しい魚介類は細々ながら食べることができる。
参考文献
・ 一柳 洋「誰も知らない東京湾」農文協
・ 長崎福三「江戸前の味」成山堂書店
・ 増子義久「東京湾が死んだ日」水曜社
|