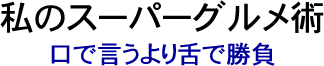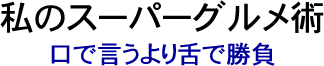|
第436回
日本の伝統食文化は継続できるか?
最近、日本の食糧自給率は
カロリーベース換算で40%に低下している。
これは、日本の食べ物の6割は
海外からの輸入を頼っていることを意味している。
他の先進国では、2002年の統計を見ると、
フランスが頭抜けていて130%、アメリカは119%、ドイツが91%、
イギリスが74%となっており、日本がダントツに低い。
日本では、食料自給率は1965年にはまだ73%あったのが、
ずるずると年々低下をしてきた。
どんな食料の自給率が低くなってきたかというと、
肉類と魚介類が激減している。
肉類は1965年は90%の自給率であったのが、
2005年の概算では55%。
魚介類は100%から49%にまで落ちこんできている。
主食の米はさすがに政府の統制によって
95%という高い自給率を維持しているものの、
野菜は1965年度が自給率100%だったのが、
現在では80%に下がっている。
美味しい食料が海外から入ればそれでいいと言う人もいるだろう。
また、国際協力が得られなくなって、
日本が孤立したときに生きていけないという議論もある。
しかし、一番問題なのは、低い自給率というのは、
日本の伝統的な農業と漁業が衰退していることを示していることだ。
農家が農業離れをしていることは、
農家経済の調査結果からも読み取れる。
1965年には農家の農業による所得は、
総所得の43.7%だったのが、1970年には17.0%、
そして、ここ数年は13〜14%と低い値になっている。
実際、栃木県で蕎麦栽培を行っている畑の周囲には、
農家の若者はほとんどいない。
たいていが都会へでて、会社へ勤めている。
何故かというと農業だけでは、自給自足はできても、
子供を学校に入れるための費用などが出ないからだ。
農家が作った農作物は各地のJAに収められることが多いが、
その単価はとても安い価格で、
とても儲けられるようなものではない。
栽培と品種にこだわり、品質を高くして、
高く売ればいいかというとこれがまた、難しい。
昨年行った蕎麦の契約栽培では、畝幅を広くとり、
手刈り、天日干しの手作業にこだわったが、
人件費まで考えると、
通常の流通している蕎麦粉の数倍の価格になってしまった。
他の農作物でも、儲けを出すことは結構難しいのではと考えられる。
ある程度機械化をして、
品質の高さと、コストのバランスを取っている農家も
最近でてきた。
例えば、古河市にある森ファームは、
広大な作付け面積で蕎麦や米や野菜を栽培していて、
品質はとてもいい。
今後の日本の伝統食文化が維持されるためには、
農業、漁業を再び盛り上げることが必要だが、
ある工程を機械化することで、
コストと品質のバランスをとることが、
ベストな回答になるかも知れない。
|