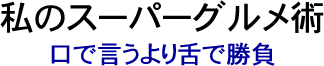
“蕎麦屋酒”の著者がプロ顔負けの美味探求
|
第63回 私が学生時代を過ごした昭和40年代では、 大学院を終えて自動車メーカーに就職した 当時、池袋から南長崎に移転した甲州屋に巡りあえて この頃に同じ蔵の酒でも様々なスペックの銘柄があること、 当時に比べると現在は地酒が日常のどこにでもある。 |
| ←前回記事へ | 2004年11月3日(水) | 次回記事へ→ |
| 過去記事へ | ホーム |
最新記事へ |
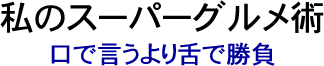
“蕎麦屋酒”の著者がプロ顔負けの美味探求
|
第63回 私が学生時代を過ごした昭和40年代では、 大学院を終えて自動車メーカーに就職した 当時、池袋から南長崎に移転した甲州屋に巡りあえて この頃に同じ蔵の酒でも様々なスペックの銘柄があること、 当時に比べると現在は地酒が日常のどこにでもある。 |
| ←前回記事へ | 2004年11月3日(水) | 次回記事へ→ |
| 過去記事へ | ホーム |
最新記事へ |