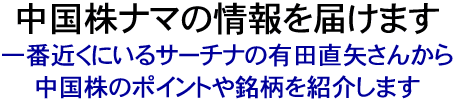|
第416回
1人あたり収入低下抑制に自信示す中国移動
中国移動(香港)有限公司
(チャイナモバイル、0941)の
王建宙・董事長は05年5月、
ARPU(1契約当たり月間平均収入)の低下について
見解を発表しています。
ARPU低下の現状について、
同社としてはコスト調整を綿密に行っているので、
05年に入ってからも
月間300万件以上の新規加入が続いている中で、
それらの粗利益率は
満足できる水準を維持している、
と述べています。
また、無線データ通信事業でも
予測を上回る業績を上げており、
SMS(ショート・メッセージ・サービス)や
MMS(マルチメディア・メッセージ・サービス)、
着信メロディのダウンロードなど
各種コンテンツの充実を図ることで、
ARPUの低迷を抑えることは
十分に可能であると説明しています。
前回までに紹介したARPUの急速な低下が、
今後の中国移動の業績の不安となる指摘が
杞憂になればよいのですが。
ここ数年、消費者物価指数(CPI)や
商品小売販売価格指数では、
IT関連項目の指標は
いずれもマイナスを示しており、
04年、CPIが高水準となって
インフレ懸念が広がった時においても、
IT関連の項目のみは
−1%〜−3%程度の水準で
推移するといった具合です。
商品小売販売価格指数の方は、
より顕著なマイナスを示しています。
毎月の指標は前年同月比
−7%〜−10%の間で変動しています。
単純にIT関連の商品やサービスの小売価格が
年間7%〜10%低下しているともいえます。
これは明らかに、
通信に関する商品やサービスの物価、
あるいは販売価格といったものが、
低迷していることを意味します。
この傾向が、
今後急速に回復する見込みは少なそうです。
業界にとっては、単純に、
商品やサービスの価格が上向かなければ、
利益の確保にとって
厳しい状況になるといえます。
それでも私個人、
中国の通信業界の前途は明るいと考えています。
その根拠はやはり
莫大な市場のキャパシティです。
そうした意味で、中国移動も長期的に見ると、
当然のことながら有望銘柄です。
そのためにも、新規加入件数に一喜一憂するよりは、
やはりARPUの過剰な低下を防ぐ方法に
もっと熱心になるべきであり、
こうした状況だと、
たとえ第3世代携帯電話(3G)が始まったとしても
高収益サービスを展開、持続することが
難しいことも考えられます。
ARPUの低下を
今の半分ほどにでも抑えられれば、
中国移動の業績や営業構造も
かなり変革されたということができるでしょう。
|
−消費者物価指数(CPI)と商品小売販売価格指数、それぞれのIT関連項目の推移−
|
 |
※IT関連項目
それぞれの指数の「交通と通信」という項目。
交通も含まれているため、通信だけの指標ではないが、
現在の中国における家庭の消費支出状況における
交通と通信の割合などを勘案すれば、
通信への比重が大きく、
ここでは便宜上、この項目をIT関連項目とした。 |
|