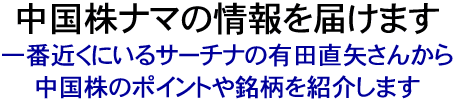|
第260回
「消費」<「投資」 今後数年、格差は拡大傾向に
2002年を境に、
中国の「投資(固定資産投資総額)」と
「消費(社会消費財小売総額)」の強弱が
よりはっきりとしてきます。
02年に「投資」額が「消費」額を上回りました。
「投資」額が4兆3499.9億元に対して、
「消費」額が4兆910.5億元です。
両者の逆転は1994年以来のことです。
02年の両者の成長率は、
「投資」が16.9%であるのに対して、
「消費」は8.8%にとどまっています。
その後、「投資」と「消費」の格差は広がる一方で、
実額ベースで、03年には1兆元以上、
04年には2兆元近くまで、
「投資」は「消費」を上回ることになりました。
これに対して、中国政府は経済の過熱感を指摘、
引き締め策を講じて、
投資過熱抑制に乗り出した、というのが、
昨今の中国経済の大きな流れになっていくわけです。
この両者の関係が今後どうなっていくかが、
中国経済を見極めていくうえで、
重要な指標になってくるはずです。
私見では、相対的な「消費」低調、
「投資」過剰傾向は今後も続くことがよそうされます。
前回も指摘しましたが、
04年の「投資」の成長率が25%を超えたのに対して、
「消費」はわずかに10%程度。
05年は、経済の急成長自体に歯止めはかかるとはいえ、
「消費」がやはり10%程度の成長を維持したとしても、
「投資」は、今までの惰性もあって、
15%成長を下回ることはないと見られていますから、
ただでさえ、実額で「投資」が大きい上に、
成長率でも「投資」が上回るということになれば、
格差はますます広がることになります。
以前にもお話したとおり、
中国の現段階において、
「投資」が先行するというのは
決して異常なことではありません。
インフラ整備に対する投資は、
今後の中国経済の成長を考える上では、
今、ある程度は必要なことです。
ただし、それも限度があります。
要は、あまりにも「投資」が
過熱しすぎるようであれば、
調整が必要で、
それに対する警戒は、
04年に引き続き、05年も、あるいは06年も
中国の重要な課題になってきます。
|