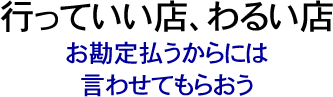|
第135回
鮨屋のタブーに挑戦 その4
評価は修行年数よりネタの良し悪しだけで決まるのか
慢性的な不景気で、
飲食店業界も決して楽ではないと思うのですが、
それでもどんどん新店や分店がオープンしています。
そして、最近目につくのが新しい、
そして若い主人の「鮨屋」の開店です。
山本益弘氏の言い方をまねれば、
今年の「スシヤ オブ ザ イヤー」になるかもしれない
「さわ田」。
多くのフードジャーナリストも褒めている「あら輝」。
そんな事までするかと思いますが、
わざわざ小田原から食べにきたという客に遭遇した
「神泉 小笹」。
いすれも30代か、いっても40チョイすぎの若い主人たちです。
つまり、何十年も他の店で修行して
満を持して開店したというものではありません。
最近は、鮨屋の評判には、
修行年数はあまり関係ないのではないでしょうか。
「さわ田」の主人は、ある週刊誌の編集者を通して、
8年前に「青木」では半年くらいしか働いていない、と
言ってきました。
「神泉 小笹」も知人からの話ですが、
本店の「小笹寿し」での修行年数は少ないと聞きました。
「あら輝」の主人も2店ほど修行にでていたと
本に書いてありましたが、
年から考えてそんなに長い期間だったとは思えません。
つまり、この道何十年といった職人たちではないのです。
でも、今、これらの店を悪く言っている人は見かけません。
私も立地や営業形態は別にして、
「さわ田」はうまいと思いますし、
「あら輝」や「神泉 小笹」もそのコストを考えたら
CPは充分です。
特に「さわ田」は、ネタを青木の時代のルートではなく、
独自に開発したとやはり編集者から聞きました。
つまり、過酷な修行や、長い年数を要しなくとも、
ネタルートを確保し、原価率を上げて仕入れれば、
皆から評価される鮨屋になるのではないでしょうか。
握りの技術が云々といっても、
ネタが悪ければ意味がありませんし。
よく神様?小野二郎氏の
「握り」の技術のことを書いた本を見かけます。
しかし、ネタやその江戸前の仕事を評価する記述はあっても、
上記3人の「握りの技術」を述べたものを
私は読んだ記憶がありません。
つまり、手っ取り早く鮨屋の評判店にするには、
いわゆる彼らの言葉で言う、「志が高い」というのでしょうか、
早い話、良いネタをケチらずに仕入れることが先決のようです。
ピッツァや蕎麦のように、
今後は鮨屋でも、ますます若い主人の店が出てきそうです。
|