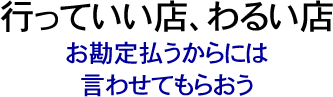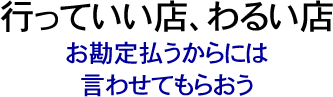|
第64回
料理評論家、フードジャーナリストの習性・実態 その5
不必要な料理人へのヨイショ
最近料理人の本が目立ちませんか。
小野二郎氏の確か「旬を握る」は
8000部ほど売れたと聞いています。それにあやかりたいのか、
「みかわ」や「竹やぶ」もだしてきました。
これらの本に共通しているのが、口語体の文章と
後半の部分をしめるQ&Aというか座談会です。
なかなか時間がとれないので彼らのしゃべりを口述筆記し、
ボリュームを確保する為に座談会をはさんでいるのでしょう。
特に二郎さんの本は、ネタの旬というものの考え方、
鮪の部位やさばき方など参考になるところがありました。
独特の価値観、接客方針などのお仕着せには閉口しますが。
これらの本は、彼ら料理人本人が書いていることに
なっていますから、鼻につく驕った口調、
勘違い発言などに目くじら立てて取り上げることはありません。
買って読まなければいいのですから。
しかし、おいしい店に行きたい、と参考に買った料理店評価本、
ガイドブック、配信メール(有料)における、
料理評論家、フードジャーナリストの
臆面もないヨイショ記述は問題です。
店構え、雰囲気、食材、料理の味わい、サービス、
酒類、価格、経営姿勢などのバランスを考えて評価すべきですが、
彼らはやたらと料理人との親密感を強調した記述をします。
料理人の本心ではない、その場凌ぎのPR口上や
修行歴をそのまま垂れ流し、
いかに仲が良い、信頼されているかを述べたがります。
料理人に迎合することによって、
今後もおいしい「特別料理」の提供と、
ライターとしての今後の地位安定を狙っているからでしょう。
でも、読者や一般客にとって、実態のともなっていない
彼らライターの「ヨイショ記事」は
まったく意味がないのはおわかりですね。
鮨業界では「神」にまで祭り上げられた二郎氏の
「神業」などを詳しく述べようと企画している山本益博氏も、
マーケティングしているのでしょうか。
心技体が伴わない人を「名人」として
「神」として祭り上げるその究極の「ヨイショ」に
私は大きな疑問を持つのです。
一見客や常連でない客に対する「客を客とも思わない」経営姿勢。
そして傲岸不遜な発言。
一度でも店を訪問した客で、
二郎氏親子に「人柄の良さ」を感じ取る人がいるとは思えません。
なぜこのような料理人たちをあたかも
「極めた人、完成された人」のように持ち上げて紹介するのか、
公に疑問を呈する人が少ないのが残念です。
|