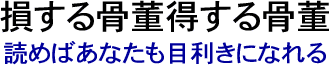|
第169回
儲かる骨董−実行編
2、骨董もブランド志向
 |
|
古伊万里吹墨の兎(イメージ)
|
骨董に流行り廃りがあるといえば、
知らない人は「へぇ〜!」とびっくりする。
骨董と言うからには
最低でも150〜200年くらい経っていなければならない。
僕らが取り扱う品は、1000年や2000年経っているのはザラ。
だからそんな古いものに流行があることは、
あまり知られていない。
しかしきっちりあるのだから用心しなければならない。
価格が大幅に動くのだ。
僕の骨董経験はせいぜい30数年のこと。
この道50、60年も経験した人なら
流行り廃りの大きな波を5、6度はくぐっているはずだ。
それでは僕なりの経験を書いてみよう。
30年ほど前、Y先生という古伊万里の研究家がいた。
本業はお医者さん、風貌は経済評論家の内橋克人先生に似ている。
その先生が古九谷、有田説を発表された。
業界は、このことでかなりにぎわった。
さらにY先生は古伊万里の本をどんどん出版され、
次々と新しい切り口を展開していった。
事実を検証し、それまで古伊万里という
大雑把なくくりであったものを、
初期伊万里・盛期伊万里などと時代も分類し、
魅力的な伊万里の世界を世に問われた。
すると初期伊万里など、
それまであまり注目されなかった作品が大きく値を上げだした。
初期伊万里(161年頃〜1670年頃)の吹墨の兎の図などは、
直径21cmくらいのもので
焼き上がりが良いと300〜350万円位するようになった。
こうなると火がついたように
皆初期伊万里の作品を求めるようになった。
「先生、初期の良い皿ありませんか?」と尋ねたところ、
「沢山持っていたが、もう一枚もないよ。
次は中期だな!僕は今『盛期の伊万里』という本を書いている。
絵付の良いのを買っておきなさい。」と手の内を見せてくれた。
「それ2、3点譲ってください。本に収録されるのを」と言うと、
「自分で集めなさい」とびしっと決められた。
そのブームに乗って、多くのコレクターが盛期伊万里を買った。
その兎の皿は今せいぜい120〜150万くらいだろうか?
骨董のマーケットなんて狭く、浅いものだ。
誰が何をやっているか注意しているとよく見える。
株や土地、金なんかよりよほど分かりやすい。
マーケットが巨大だとどうしても色々な要素が絡んでくる。
骨董は値下がりのカーブもまたゆっくりとしている。
敏感なコレクターが売りに回っているときでも、
他のコレクターはまだせっせと買っているという調子だ。
美術館の展示や出版物、雑誌の特集などに目を配り、
熱が上がる前によい物を選び、そしてピークを逃さず売る。
こんな目配りをしながら骨董を楽しもう。
ブランドはこうして作られる。
魯山人、九谷、ガレーやドームなどのアールヌーボ、
この20年ほどの間に色々なブームが何度か生まれ消えている。
|