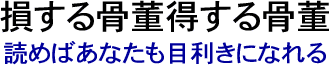|
第57回
商品学(タイ編)
3. タイの仏像 贋作の微笑み(II)
13世紀末から15世紀にかけて、
スコータイ朝はほぼ今のタイ国の領土を
支配するようになると、セイロン島から仏教を将来した。
顔は卵形で、しなやかな美しい体型の
仏像を製作するようになる。
国力が充実したのか、
かなり大型の黄金仏などもこのとき作られている。
現在バンコクのワット・トライミット(寺院)にある
黄金仏などはこの時代に作られたものだ。
高さ3メートル、重さ5.5トンの巨大な黄金仏は
金の純度が60数パーセントあるといわれ、
黄金の時価評価に直して100億円を超えるものといわれている。
この仏像はスコータイの拝辞にあったといわれ、
全体が漆喰でカバーされていて
1953年、大嵐の際にクレーンが当り、
剥落した漆喰の下から
ギラリと光る黄金の肌が発見され
バンコクに運ばれたといわれている。
これほど大きな黄金仏を作り上げたスコータイ時代は
タイの歴史の中でも飛びぬけて強力な王国であった。
従って仏教美術の様々な作品は優美な作品が多い。
タイの人々はこの時代の作品を好み、
ちょっとした仏像でも結構高価である。
ちょうど我々日本人が
平安、鎌倉の仏教美術を好むのと似ている。
ついで、14世紀後半から17世紀はじめ頃まで
過剰な装飾を施したアユタヤ仏が生まれる。
15世紀頃はスコータイの影響を濃厚に受けているが、
16世紀以後は
宝冠を頂いた独自の形を持つようになってくる。
タイでは国立博物館や地方の美術館に行っても
展示品の70〜80%は仏像だ。
その他仏教関連の美術品を加えると
展示品の殆ど全てが仏教美術に関するものだ。
それだけにタイの仏像や関連美術品は優れたものが多い。
タイ南部には7〜9世紀頃の
シュリビジャヤの作品があり、
東北部にはクメールやダヴァラヴァティの
7〜9世紀頃のヒンドゥーや仏教美術の作品がある。
また12〜13世紀にはロップリ時代と呼ばれる
クメール後期の仏教美術がみられる。
それらの像の魅力はここでは紹介しきれないが、
タイ国の人々は仏教を厚い信仰心で守っている。
それだけに良い像は昔から結構高価であって
なかなか海外に出にくい。
高さ15〜20cmくらいのコンディションが良い
14世紀頃のスコータイ仏など100〜200万もする。
40〜50cmぐらいのモノになると
強気のディーラーは1000〜1500万くらいの値をつけるのだ。
日本でもちょくちょく店頭で見かけるが
殆どの作品がコピーかコンディションの悪いものだ。
気をつけよう。
また持ち出しも厳しい制限が課せられている。
 |
 |
|
14世紀 スコータイ仏
|
7、8世紀 ダヴァラヴァティ仏立像
|
|