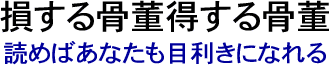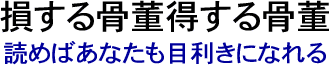|
第50回
商品学(ベトナム編)
5.ベトナム陶磁II
―小林一三も家康もみんなあこがれた安南茶道具
日本人は陶器好きだと多くの人は言う。
その底流に茶の湯文化がある。
自分の気に入った茶碗で茶を一服いただくと、
ほのぼのとした喜びがわいてくる。
両手で茶碗を抱え、茶を喫する文化は
恐らく日本だけであろう。
少し距離を置いて見つめてみる。
日本人の陶器好きということは、
用いるということに
ある種の価値観を置いているように思われる。
だから商売をやっていても
徳利とかグイ呑み、茶碗や香合など使えて楽しいもの、
それに加えて時代があるものに人気が集まる。
さらに伝世とか著名な歴史上の人物が所持していたなどの
付加価値が加わると、とてつもない値段が付くようになる。
ヨーロッパのように単純な鑑賞一辺倒ではないのだ。
そんなわけでベトナム陶磁についても
茶の湯に用いられる器が良く売れる。
安南絞手茶碗と呼ばれる染付で高台が高い茶碗がある。
このタイプのコンディションの良いものは
一碗70〜100万円近い値のつくものがある。
何故そんなに高いかと言うと、
江戸時代に日本に渡って来て
大名家や豪商に大切にされていた茶碗がある。
それを幕末頃に著名な陶芸家達が写して
非常に人気を博したのだ。
まだ議論の余地はあるが、
蜻蛉をデザインした茶碗なども
その手のものではないかと僕は想像している。
茶の湯は桃山時代頃に利休という天才的な茶人を生み、
様々な国の陶磁器や漆、金工作品を茶の空間に囲い込んだ。
それは南蛮貿易という交易の中から生まれたものである。
ベトナムの陶磁器もそのような背景から
茶の湯に取り入れられるようになったのである。
写し物を数多く製作したために、
貴重な南海交易品の安南絞手茶碗(本歌)が有名になり、
それを強く求める風潮が幕末頃出来上がった。
その多くの茶人があこがれた
安南絞手茶碗を見つけたエピソードを紹介しよう。
 |
| 14、15世紀 安南染付鉢 |
|