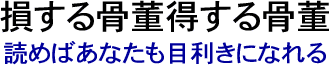
「骨董ハンター南方見聞録」の島津法樹さんの
道楽と趣味をかねた骨董蒐集の手のうち
|
第40回 遼は契丹人が起こした遊牧民の国である。 彼らの作った陶磁器は草原の民らしく 10世紀はじめから12世紀初頃の 15年位前に我国で中国の美術館からもたらされた 市場に出回っている遼三彩は仔細に観察すると |
| ←前回記事へ | 2004年11月1日(月) | 次回記事へ→ |
| 過去記事へ | ホーム |
最新記事へ |
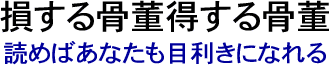
「骨董ハンター南方見聞録」の島津法樹さんの
道楽と趣味をかねた骨董蒐集の手のうち
|
第40回 遼は契丹人が起こした遊牧民の国である。 彼らの作った陶磁器は草原の民らしく 10世紀はじめから12世紀初頃の 15年位前に我国で中国の美術館からもたらされた 市場に出回っている遼三彩は仔細に観察すると |
| ←前回記事へ | 2004年11月1日(月) | 次回記事へ→ |
| 過去記事へ | ホーム |
最新記事へ |