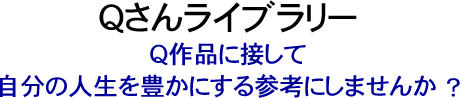|
第213回
日本は省エネと自動化で石油ショックを脱しました
邱さんが長く対立関係にあった台湾の国民政府から請われて、
帰国したのは昭和46年のことです。
邱さんは故郷の経済建設のため獅子奮迅の働きをし、
日本の事業経営者を呼び込み、
自分もお金を出して、多くの事業を展開しましたが、
昭和49年、50年に世界を襲った石油ショックのため、
多くの事業を整理したことを紹介しました。
昭和55年、6年のことですが、その頃から
邱さんは日米間で貿易摩擦が激しくなると予想し、
そのことに焦点をあてた作品を書くようになります。
それらの作品の紹介に入る前に、
邱さんが昭和61年に出版した
『失敗の中にノウハウあり』に書かれた文章を読んで
その背景について勉強しましょう。
「(石油の値上げで)産油国は
お金をしこたまふところに入れたつもりでも、
次の支払いをするときはその分だけ
高く支払わなければならないから、
言ってみれば、日本という壁に向かって
テニスの練習をしているようなものである。
『強く打てば、強く返る』というのが
加工国を支配する原則であると私は見た。
ただそうは言っても、石油の値上がりで、
加工製品のコストも軒並み高くなった。
石油が暴騰しただけでなく、
物価が暴騰すると賃金も暴騰するし、
一年に賃上げが35%にも及んだことは
私たちの記憶に新しい。
このコスト・インフレは
日本だけで起こっているわけではないから、
韓国や台湾へ引っ越したからといって片づくわけではない。
しかし、さしあたりカメラでも腕時計でも、
工業製品の売値を値上げすれば、
ただでさえ家計費の中で
エネルギーへの出費が増えているときだから、
売上げがダウンすることは目に見えている。
またニュージャパンと言われている国々も、
石油ショックの影響を受けている点では
全く同じとしても、
人件費などのコストが日本よりも低ければ、
日本から工場がもっと続々と海外に移動して
国内が空っぽになってしまう懸念もある。
少なくとも昭和49年、50年の時点では、
日本の工業界があげてこの二つの恐怖と
闘わなければならなかった。
日本人はこうしたピンチに直面すると、
いっそう団結も堅くなるし、
一致協力して困難にあたる気質を持っている。(中略)
日本人が新しく考え出したピンチ切り抜けの具体策は、
一つは省エネであり、もうひとつは自動化であった。
具体的には、『軽薄短小』化であったり、
ガソリン消費量の少ないエンジンに切り替えることである、
またこれらのものを製造するのに、ロボットを採用したり、
無人工場をつくることである。
こうした起死回生策のおかげで、
日本は物の見事にピンチを脱け出しただけでなく、
一段と国際競争力を身につけることに成功したので、
今日の経済社会では、資源国よりも
付加価値を創造する国のほうが
遥かに有利な立場にいることを
全世界に向かって証明することになった。」
(『失敗の中にノウハウあり』)
|