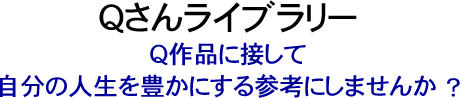|
第115回
邱さんの小説では主人公の懐具合が明瞭です
小説家として活動した三島由紀夫さんは
天国に逝ってしまいましたが
同じく小説家として作家活動をしてきた邱さんは
変貌を遂げていきます。
「『金儲けのセンセイ』『株の神様』として
名が知られるようになればなるほど、
私の小説は次第に売れなくなった。
私が小説を億劫がるようになったせいもあるが、
嶋中鵬二さんによると、
『高級すぎて一般うけしない』からであり、
また安岡章太郎によると、『あんまり本当のことをいいすぎて、
読んでいるほうがうんざりしてしまうから』だそうである。」
(私の金儲け自伝)
さて、昭和46年に「邱永漢自選集」を出すことになり、
邱さんは前年の昭和45年の暮に、
昔書いた自分の小説を読み返し、
自分の書いた小説に一つの特徴があることに気づきます。
「45年の暮れ久しぶりに昔書いた短編小説を何十篇か
恐る恐る読み返してみたが、
意外にも途中で巻をとじるような
ぶざまなことにはならなかった。
中にはこんな駄作をどうして書いたのだろうかと
首をひねりたくなるようなものもないではないが
(それは私の学校時代の恩師が長期の療養生活をやることになり、
その療養費を払ってあげるために恥をさらしたものであるが)
なかにはサマセット・モームとどっちかといった
緊張感に満ちた作品もいくつかあった。
どうして臆面もなくそういうことが言えるかと、
十数年もたってみると、昔書いたものなど
もうすっかり忘れ去っており、まるで他人の作品を読むような、
第三者的な立場で自分の作品を読むことができたからである。
小説は世間を反映するものだ、と言うけれども、私の小説も
私がそれを書いた時代のことをあれこれ想い出させてくれる。
しかし、いま読み返してみると、その頃は気がつかなかったが
どの作品にも共通していることは、主人公の懐具合が
はっきりそれとわかるように明確に書いてあることである。
たとえば『南京裏通り』は横浜の中華街で
バーを経営しているシンガポール生まれの女が、
戦争中に同棲していた日本兵のあとを追って
北海道の旭川に着いたときは、いくら持っていたか、
生活力のない男の納屋に住みついて
炭焼きと養豚をやって金を稼ぎ、
金を持って男のもとを去るときは、いくらもっていたか、
そして、南京街の裏通りのバーにつとめているうちに、
バーの経営者から月賦でバーを買いとったときはいくら払ったか、
ということが全部読者にわかるように書いてあるのには、
われながら驚いた。やはりお金に対する几帳面な態度が、
あの時代にも底流として流れていたようである。」
(『私の金儲け自伝』)
邱さんの小説を読まれる際、はたしてそのとおりかどうか
チェックしてみるのも楽しいことですね。
|