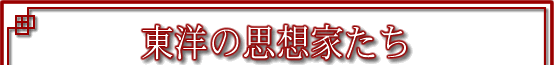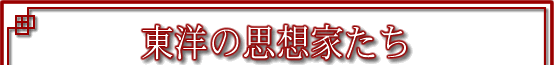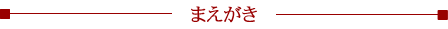 |
この本の初版が講談社から出版されたのが一九五八年だから、既に三十九年の歳月がたっている。この間、徳間書店から出版された「邱永漢自選集」全十巻の中にも収録されたし、日本経済新聞社から出版された「Q
BOOKS」全二十五巻にも収録されているから、今度で四度目のおつとめになる。
執筆した当時の私は三十代のはじめだったが、歳月は容赦のないもので、あッという間に七十代になってしまった。この年まで馬齢を重ねて見ると、何千年も歴史の陶汰に耐えてきた大思想家たちの物の考え方を大した社会体験もない生意気盛りの青年があれこれあげつらうのは、いささか身の程知らずだったという気もしないではない。現に私が書きあげた原稿を創元社に持ち込むと、社長さんとも親しかったにも拘らず、体よく断わられてしまった。あとできくと、創元社に強く発言権を持った小林秀雄氏がフンと笑って相手にもしてくれなかったのだそうである。
私よりもずっと年も上で、私よりはうんと社会経験を積んだ小林さんから見たら、私のような試みは大胆不敵に見えたに違いない。それでも別の出版社が引き受けてくれたので、私の青春の冒険は陽の目を見ることができた。
ふつう古典というものは若者に人気がなくて、功成り名遂げてやることのなくなった老人のお説教のタネ本に使われるものだが、三十代の私はそれをアダム・スミスやマルクスの本を読むようにむさぼり読んだ。中学の漢文の時間に押しつけられて読んだ時と違って、私には新鮮で議論の対象になるような内容のものに見えた。
三十代は若いというけれど、その時に受けた印象と、いま原典を読みかえして受ける感想はそんなに違ったものではない。あるいは私が年輸を重ねても一向に成熟していないということになるかも知れないが、人は必ず若い時があるものである。だから若い時にはこういう解釈も可能なのだ、と寛大な気持で読んでもらえれば有難いと思う。
|
| (一九九七年十二月記) |
|