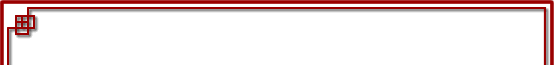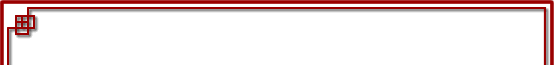人間、ひとたび生を受ければ、燃え尽きるまで生きるべきものを、物と相たたかってやまず、生の道を駆け足でとめどもなく走り去って行く。終身あくせくとして、しかもたいした成果も上がらず、疲れ果てて落ち着くさきも見あたらない。これでは死んでいないといったところで、なんの意味があろう。いったい、生を受けるということ自体が本来かようにとめどもなきものなのだろうか。それとも自分ひとりだけが惑いに惑って、他の人は惑わないものだろうか。
ではなぜ、こう惑いが多いのだろうか。ゆうゆうとこだわりなく生きていく方法を教えてくれる師がいないからだろうか。いやいや、体が作られたように、心もまた作られたものだ。自然に作られた心に任せ、それを師と仰げば、なんでよき師のいないことを嘆く必要があろう。なんで感情の動きを知って、そのなかから取捨選択をする必要があろう。
「自然心」は愚者にさえ備わったものだからである。
そうした自然心を悟らず、是非にこだわるのは、今日、旅に出て、昨日、着くようなものである。ありうべからざることをあると主張するのだから、どんなりっぱな先生が現われても、これを納得させることはできないにちがいない。
ことばというものは風が吹くのとはわけが違う。ことばにはそれぞれ意味する内容があるからである。しかし、その意味が必ずしも一定していないとすれば、はたしてことばを言ったことになるのであろうか。それともなにも言わないのと同じなのであろうか。人間のことばが雛鳥の鳴き声と違うことをいかにして証明できるのであろうか。
道にはもともと真物も偽物もない。ことばにはもともと是も非もない。行くところ道ならざるはなく、言うところ是ならざるはない。しかるに、一方にかたよると、真偽や是非が生ずる。儒家や墨家の是非善悪は目を覆われていることから起こっているのである。一方の是とするところを非とし、非とするところを是とするよりは、もともとこの世の中には是も非もないことを明らかにするにこしたことはないであろう。
人間の考えによれば物事はあれでなければ、これであり、これでなければ、あれである。
一方の立場では非のものも、べつの立場でみれば是である。だから、是は非なくては存在せず、是といっても要するに相対的な是にすぎない。とすれば、はたして是というものは存在するのであろうか。
それゆえ、聖人は是非によらないで、天に照らす。すなわち是非を超越した是も非もない是なのである。しかし、「是も非もない」という主張もまた是非の一種であるから、それはそうしたあらゆる無限の対立をことごとく包含した絶対的な是でなければならない。
かかる是はちょうど、扉の軸のようなもので、是も非もこれを中心としてグルグルとかぎりなくまわり続けるのである。
荘子の時代は詭弁論者が一派をなしていて、例の有名な公孫龍の「白馬は馬にあらず」という論法が世に行なわれていた。指といえば、親指も人差指も小指もそのなかに含まれるが、親指は人差し指とも小指とも異なるから、親指は指ではない。また、馬といえば、白馬も黒馬も赤馬もそのなかに含まれるが、白馬は黒馬とも赤馬とも異なるから、白馬は馬ではないと主張するのである。
「しかし」と荘子は主張する。「指をもって指が指でないことを証明するよりは、指でないものをもって指が指でないことを証明したほうがよいだろう。また馬をもって馬が馬でないことを証明するよりも、馬でないものをもって馬が馬でないことを証明したほうがよいだろう。なぜならば、指が指であり、馬が馬であるという主張は、指でないもの、馬でないものがあってはじめて成立する概念であるから、指でないものがなくなれば、指もまた指でなくなり、馬でないものがなくなれば、馬もまた馬でなくなるからである。だから、これを逆にいえば天地を一本の指だということもできるし、万物を一馬にたとえることもできるのである」
ところが世間では、可があり不可がある。なぜそんな区別ができるかというと、人が歩くと道が自然にできあがるように、みんなが指を指と呼び、馬を馬と呼ぶからである。それはたんに習慣でそうなっているにすぎず、およそ存在するすべてのものに不可ということはなく、非ということはない。にもかかわらず、万物の外形に惑わされて、人間はいかにしてそれを統一したものかと心をくだく。万物が実はことごとく同じものであることに気がつかないのである。
「ある猿飼いがトチノミを猿に与えるのに朝三つ夕方四つやろうと言ったら、猿どもは怒った。じゃ朝四つ夕方三つにしようと言ったら今度は喜んだ。実はまったく同じ数なのに、一方は怒りを買い、一方は喜びをもって迎えられたのである」 |