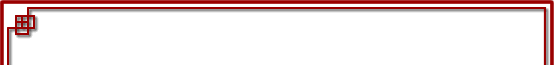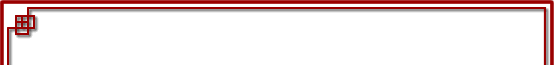齊から魯に帰った孔子は依然として不遇であった。自分の考えがなかなか世の中に容れられないので、弟子を集めて教えたりした。
魯の季氏の家臣に陽貨という男がいる。主人の季平子が死んで季桓子の代になると、若主人を自分の思うままに操って、宮廷で勢力をふるった。野心家がやることはたいてい似ているが、この男も季氏が魯君の代々の位牌に加えた罪悪を暴き、宗廟におおげさな供物をして、大義名分を明らかにしようとした。
陽貨はかねがね孔子を自分の味方に引き入れようと思っていたので、しきりに孔子に会いたがった。どうしたわけか孔子はこの男が気に入らない。こういう間柄を、われわれは肌が合わないというが、私の想像では、やり方がお互いにあんまり似すぎていたからではないかと思う。
孔子がどうしても会いたがらないので、陽貨は、孔子の不在をうかがって、豚肉を孔子に贈り届けさせた。使者から本人が直接受け取らない場合は、後日、自分で謝礼におもむくのがそのころの習慣であった。もしわれわれがいやな奴から贈物を届けられたら、なんら躊躇するところなく送り返してしまうだろう。またもしそうするだけの勇気がないならば、我慢して謝礼を述べに行くだろう。ところが孔子はわれわれよりはるかにうわてであった。彼は送り返しもしなければ、礼状も書かなかった。そして、召使をやって陽貨が留守であるのをたしかめたうえで、現代風に申せば、ちょっと名刺を置いてきたのである。
ところが、陽貨のほうでも、孔子がこんなことをしそうな気がしていたので、あわてて家に帰って来た。その途中、道でばったり出会った。
「やあ、どうも」
と孔子がきまり悪がっていると、
「せっかくですから、家へいらっしゃい。そしてゆっくり話しましょう」
それでもなお孔子が行こうとしないので、
「りっぱな才能をもっていなから、それを国家の役にたてないのは、仁者のやることじゃないでしょう」
と皮肉を言った。
「仰せのとおりです」
と孔子が答えると、
「仕事をしようと思っていながら、ぐずぐずして時機を失うのは、知者のやることですか」
「違いますね」
「歳月は矢のごとしというでしょう。早くしないと乗り遅れてしまいますよ」
そう言われると、孔子は反駁のしようがなかった。
「わかりました。近いうちに仕官いたしましょう」
これはもちろん、その場かぎりの言いのがれで、その後、同じ謀叛者の公山弗擾に仕えようとしたが果たさず、五十一になってからやっと定公に拾われて、魯の政治に参画するようになったのである。
政治家として魯の行政にたずさわったのは足かけ五年で、自分よりはるかに凡庸な君主に愛想をつかして衛へ去ったとき、孔子は五十五歳であった。「売らんかな」の生活はいまに始まったことではないが、それから以後、本格的な押し売りが始まったとみてよい。
孔子が職を求める方法は相当執拗で、いささか軽率にすぎたきらいがある。霊公よりも実権を握っている不身持ちな南子にも会っているし、国庫の実権を握る王孫賈(おうそんか)にも会っている。
「奥方にとりいるよりも、実際にかまどの番をしているこのおれにとりいるほうが賢いぜ」
と金庫番にそうひらきなおられると、さすがの孔子も気がさしたか、
「天のとがめを受けたら、祈ってもむだですからね」
と答えている。このことばは、天道にもとれば、と解釈するのがふつうだが、孔子は相当のユーモリストだから、将を射るには結局将を射ることさ、と聞こえないこともない。
というのは彼の目的は、自分の同輩とうまく馬を合わせるよりは、実権を握るほうにあったからである。しかしこの場合も、かつて魯の司寇をつとめたことのある経歴が彼の仕官の邪魔になった。
「魯ではいくらもらっていたのかね」
と霊公が聞いた。
「六万斗でございます」
「そうか」
霊公の態度から見て、それくらいはくれそうに思えたが、それきりなんの音沙汰もなかった。履歴書の前歴がものものしいとなかなか職にありつけないことは、今日でもよくあることである。 |