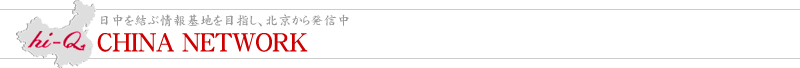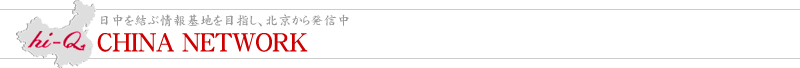|
口にまだ入れることが出来る食料ゴミが、
全食物供給量の40%に上るということに対し、
一企業として出来ることを考える時、
それは企業の事業モデルそのものに関わる話しでもあります。
前回触れたように「食べられるゴミ」は、
第1次産業である産地を先頭に、2次産業における加工現場、
そして3次産業における消費の現場でそれぞれ発生しています。
私はいま事業の発展を2つの方向性で捉えています。
1つは、3次産業である店舗の展開。
(飲食、スーパー、配送事業等)の展開。
もう1つの方向性が、1次2次3次産業を縦に繋ぐ、垂直統合、
1+2+3=6次産業の構築という方向性です。
簡単に言うと、コーヒー豆を自分で作って、
自分で焙煎して自分で売るという事がその代表です。
特に、この垂直統合モデルを展開する企業においては、
食物供給のバリューチェーン(価値連鎖)に全て関わるわけですから、
その過程で発生する無駄を自分でコントロールする事が可能なわけです。
私は、例えばこんなことを考えています。
農家で出る安全だけどスーパーや卸に売れない規格外品を買い取ります。
(もしくは、主力食材は自分で作ります。)
その後、養豚事業から出た、一般的には商品価値の低い肉を利用して、
野菜と肉を組み合わせて餃子にします。
また、レストラン店舗出る、使いにくい野菜や
肉の端材も綺麗に加工して餃子の具にします。これまた餃子にします。
これを自社レストランの商品として展開したり、
もしくは、餃子屋さんをオープンします。
そもそも、中国の街にあるような餃子屋さんでしたら、
これといった投資もかからないでしょうから、十分に勝算はあると思います。
こうして40%のゴミを30%減らして10%にすれば、
それだけで世の中に対し新しい価値を創造した事になります。
最近、食料ゴミと餃子を見ると異常に興奮して写真をとっております。
少し病気かもしれません。(笑)
|