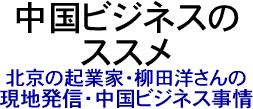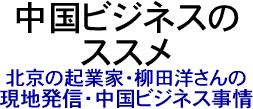|
第869回
中国は既に「世界の工場」ではない!
先日、中国綿紡績業協会が
国内17省の綿紡績企業を対象に行った調査によれば、
約半分、49.2%の企業が
生産中止や業種転換を希望しているのだそうです。
理由は、人民元為替レートの上昇加速、
原料及び労働力コストの上昇、
輸出増値税還付率引き下げなどにより、
採算が極端に悪化しているためです。
労働集約型で付加価値の低い製品を作る輸出型産業が、
中国では成り立たなくなりつつあることがわかります。
中国は既に「世界の工場」ではないのです。
日本でも明治維新以降戦後まで、
紡績業は近代産業の重要な担い手であり、
紡績会社は日本企業の売上高ランキングで
常に上位に位置していました。
それが、第一次石油ショック後、
円高や中国を始めとする生産コストの安い国の参入により
競争力を失った日本の紡績業は急速に衰退し、
今では、「紡績」は会社名として残ってはいるものの、
日本で綿の紡績をする会社はほとんどなくなってしまいました。
そして、今度は日本の紡績業を
衰退させる一因となったその中国で、
紡績業が成り立たなくなりつつあるのです。
中国政府は現在、「輸出主導」から「内需主導」へ、
「低付加価値」から「高付加価値」へ、
国内産業の大転換を行っています。
あまりに急激な転換を行うと、
たくさんの会社が一気に倒産し、
大量の失業者が巷にあふれ、
国内が大混乱に陥る可能性がありますので、
ゆっくりとゆっくりと転換を行っています。
そんな中で「輸出産業」、「低付加価値産業」の
代表格とも言える紡績業で、
経営が立ち行かなくなる企業が続出しているのは、
その大転換政策の効果が現れ始めている、ということです。
今や中国のユダヤ人と呼ばれるまでになった温州商人も、
元々は繊維と皮革を加工する町工場からスタートしています。
しかし、彼らは繊維と皮革の加工で財を成すと、
さっさと加工業を卒業、
その資金を北京・上海の不動産や山西省の炭鉱に投資し、
更に大きな財を築きました。
そうした人たちと比べると、
いまだに紡績業をやって困っている会社は、
いかにも腰が重く、時代の流れも読めていない、
と言わざるをえません。
中国政府の産業政策の方向性は非常に明確であり、
時間的な余裕も十分にあった、にも関わらずです。
繊維業界からさっさと足を洗って隆盛を極める温州商人と、
いまだに紡績業をやって困っている人たち。
この二者を見比べると、
やはり、自分の仕事が時代の流れに合っていないな、
と思ったら、その中でジタバタするのではなく、
次の仕事を始めるカネがあるうちに
さっさと商売替えをしてしまった方が良い、
ということがよくわかります。
|