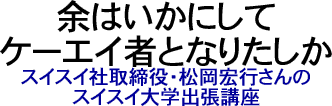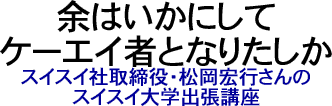|
第88回
カネカネカネのケーエイ学20:つかってもいいけど、私のもの。
 募集キャンペーンなどで、「応募作品の著作権は、主催者に帰属します」というのをよく見かける。これは著作権について、主催者の認識が不足している証拠だ。 募集キャンペーンなどで、「応募作品の著作権は、主催者に帰属します」というのをよく見かける。これは著作権について、主催者の認識が不足している証拠だ。
著作権は、もちろんつくった制作者のものである。それなのにいきなり「帰属します」というのは、応募したことで無条件に「権利を譲渡せよ」というものだ。果たして「譲渡」にふさわしい対価が払われているのか?
主催者のほんとうの気持ちは「応募作品を自由に使いたい」ということにすぎない。
多くは、そのキャンペーンやその事業に関する使用法しか考えておらず、まったく勝手に使おうなどとは思っていないはずだ。
とすれば、著作権が作者にあることを前提に、利用権がひろく主催者に設定されるとすることで、主催者の希望する結果は得られる。
したがって良心的な主催者は、「応募作品の著作権は応募者に帰属しますが、入賞作品については、本事業の宣伝活動に関し弊社で自由に使用できるものとします」と書いたりしている。
わが社では、著作権を留保しつつ、クライアントに使用権を設定するかたちで納品している。使用権の範囲については、実質的にクライアントの利便性を考え、広く設定することはさしつかえない。もちろん価格は、利用権の範囲にふさわしいものにはなるだろうが、利用権の範囲を広くとれば、クライアントの使い勝手は、実質的に「譲渡」と同じことになる。
ではなぜ、われわれが「著作権留保」にこだわり、譲渡をしないか。
われわれが心配しているのは、いったん「譲渡」してしまったら、「煮て食おうと焼いて食おうと、買った者の自由」となることである。
つまり「譲渡」した以上、予期しない第3者に譲り渡されたり、使用者の都合で勝手に内容を改変されても文句が言えない。そうなれば、作家の知らぬところで、声価を落とすことになり、次の仕事に差し支える。
もっとも、同一性保持(改変するな)の権利は、著作者人格権といわれ、理論からいえば一身専属したがって譲渡不可のはずだが、そもそも著作権を譲渡せよと主張する人に、そのような理屈が通じるだろうか。
このように譲渡は、制作者にとってリスクが大きすぎる。あくまでそんなことを主張するクライアントとはつきあうな、という考えに傾くのである。
|