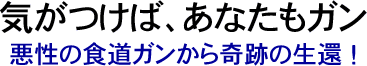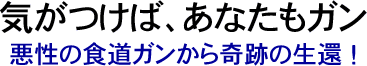|
第1538回
食育とは「欧米借り物」思想にあらず
新宿・明治安田生命ホールで開かれた
「海の精」株式会社の30周年記念講演会から
僕が感じた話の続きです。
「食育基本法」の矛盾についていろいろ書いてきましたが、
この「食育」という語源はどこから来たか?
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』で検索すると、
以下のように書いてあります。
「なお、食育という言葉は、明治時代に
西洋医学・栄養学否定運動を展開した陸軍漢方医、石塚左玄が
『通俗食物養生法』(1898年(明治31年)
「今日、學童を持つ人は、
體育も智育も才育もすべて食育にあると認識すべき」)で造語した。
数年後の1903年(明治36年)に
小説家・村井弦斎も『食道楽』
(「小児には德育よりも、智育よりも、躰育よりも、
食育が先き。躰育、德育の根元も食育にある。」)で使用したが、
この2人以外による明治~昭和初期の使用例は、
未だ発見されていない」
さて、明治初期の陸軍漢方医・石塚左玄とは、
西洋医学の医者が治せないような病気を
食べ物を変えることによって治した医者です。
わが国の食養医学の礎を築いた人で、
食養生の祖、
マクロビオティック玄米菜食法の始祖といわれる人です。
『通俗食物養生法』は、明治から大正にかけて版を重ねた
大衆向け食養解説書で、
蛋白質、脂肪、糖質のカロリー栄養学理論に対し
ナトリウム、カリウムという「二大ミネラル」で
食物と体について研究した理論を残しています。
(1)食本主義-=人間のからだは食物が作る。
したがって食物で病気は治せる
(2)穀食主義=人は歯の形から考えて、
主として穀物を食べるべきだ
(3)身土不二(しんどふじ)=住んでいる土地で
採れたものを食べる、
あるいはその季節に出来たものを食べるという原則
(4)一物全体食(いちぶつぜんたいしょく)
=食物は丸ごと食べましょうという理論
(5)三白追放=白砂糖、白米、白パンなど精米あるいは
精製した白い食品は体には良くない・・・
こうした原則を「食養生」「食育」のもとしたのですが、
より具体的な理論が陰陽調和論=
「ナトリウムとカリウムの調和論」です。
●ナトリウム(Na)とは
食塩や、肉・卵・牛乳・魚貝などの動物性食品、
●カリウム(K)とは
穀物・野菜・果物・海草などの植物性食品のこと。
「この摂取のバランスが心身の状態に大きく影響する」
としたわけです。
つまり、人体の細胞の外側には
陽性でしめる性質のナトリウムが多く、
内側には陰性でゆるめる性質のカリウムが多い。
その割合が、ナトリウム1対カリウム5程度のバランスで
保っている人が健康であること、
さらにそのバランスを持っている
最も人体に適している食物が玄米だ――、
と発見したわけです。
日本人であれば、これくらいの語原や由来を知ってから、
健康と食事、いのちと食事、
日本人らしい豊かな生活、さらに「食育」・・・
ということを考えるべきだと思います.
なぜならば、マクロビオティック玄米菜食法も然りですが、
浅薄な「欧米の借り物」の栄養思想ではなく、
日本人が、日本人の体質と風土をしっかりと観察した上で
考え出した「いのちのキーワード」だからです。
もちろん、玄米がよいといっても、
いまは化学カリウム肥料まみれものが席巻していますから、
有機農法のおコメをどう作るか? どう入手するか?
とくに幼児にどう食べさせるか?
こうした「食育」の緊急課題が、
役所では避けられていることが、とても問題だと思います。
|