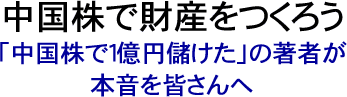|
第1179回
相対的貧困率
相対的貧困率は1980年代半ばから上昇しており、
雇用の崩壊とともにホームレスや母子世帯など
社会的に弱い立場にある人々が真っ先に貧困化してきています。
1990年代からは正規労働者における格差が拡大していない一方で、
正規労働者に比べ賃金が低い非正規労働者が増加し、
非正規労働者間の格差が拡大しており
勤労者層の格差を拡大させています。
厚生労働省が10月20日に初公表した「相対的貧困率」では
平成19年は15.7%で、7人に1人以上が貧困状態でした。
18歳未満の子どもの貧困率は14.2%となっていました。
相対的貧困率とは、
可処分所得がその平均値の半分に満たない人の割合を示す数値で、
高いほど貧困層が多い国になります。
OECD加盟国の中でメキシコ、トルコ、アメリカに次いで
日本はワースト4位になっていました。
日本はGDP世界第二位の経済大国であるはずですが、
それを我々国民が実感できてはいないのではないでしょうか。
2008年の国民生活基礎調査では、
日本の一世帯当たり年間所得の中央値は448万円の半分、
224万円以下が相対的貧困率の対象となります。
また、年間所得が200万円未満の世帯の割合は
18.5%となっていました。
どちらにしても恐ろしい数字です。
日本の経済では個人金融資産は1400兆円ありますが、
国債及び借入金債務現在高は861兆円程度となっており、
このままいけば逆転していきます。
個人金融資産より国の借金が多くなっていきます。
だいたい、国民のお金を当てにして
借金があっても大丈夫だと言っている国のほうが
少しおかしいのですが。
日本の借金が多くなって破綻しそうになったら
海外のお金は日本から逃げていきます。
「泥舟から鼠は逃げ出」していくのと同じです。
また、今まで「ぬるま湯に入っている蛙」と同じで
茹であがりそうになったときにあわてても
もう遅いかもしれません。
その解決方法としていずれ消費税が引き上げられていくでしょうが、
将来は段階的に引き上げられていき、
現在の5%から10〜15%と上がっていくでしょう。
民主党は4年間は引き上げないとしていますが、
4年後以降は上げていく可能性がでてきます。
|