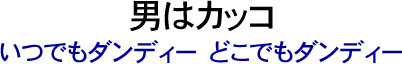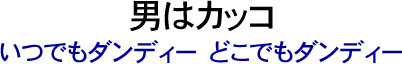|
第891回
さあ月見のはじまりです
月をゆっくりと眺めたことがありますか。
秋は名月の季節。
8月15日(陰暦)が「十五夜」で、
9月13日(陰暦)を「十三夜」と
むかしから言ったものです。
十三夜が「後(のち)の月見」で、
これだけを観るのを
「片(かた)月見」と呼んだのだそうです。
<月見する座に美しき顔もなし>
という芭蕉の俳句があります。
でも、これを誤解してはいけません。
最初、芭蕉は
<名月や児(ちご)立ち並ぶ堂の縁>と詠んだ。
寺の美少年と名月を対比させた。
次に
<名月や海に向かへば七小町>とした。
これにも納得しなくて、ついに
<月見する座に美しき顔もなし>
にたどりついた。
つまりその位美しい月だなあ、という句なのです。
美少年や美女よりも
名月のほうが美しいかどうかは、
この際、話を横に置いておきましょう。
どの位、月が美しいのか、
一度とっくりと鑑賞してみようではありませんか。
どうせなら1人で眺めるのもなんだから、
気の合う仲間4、5人と誘い合って、
ベランダか屋上か庭あたりで宴を張りましょう。
これを観月会と昔の人は言ったのです。
もう少し優雅に呼ぶなら「月の宴」。
ゲストのことは「月の客」。
しかしまあ、そうはいっても
結局のところ私などは
名月をサカナに酒を飲んだり、
佳肴に手を伸ばしたりするほうが忙しいのですが。
中国の風習を手本として
日本でも広く定着したのが平安時代というから、古い。
古いからというだけでなく、
せっかくの「月の宴」を廃れさせてしまうのは
惜しいではありませんか。
中世には中世の、21世紀には21世紀の
月見のやり方がきっとあるはずです。
月の宴の予定が決ったなら、
まずは案内状を作りましょう。
電子メールもよろしいが、
地球の進歩に月が驚くといけないので、
ここはひとつ葉書あたりをおすすめしたい。―
そうなると月の宴の前に、
はやくも万年筆にしようか筆にしようかと、
雅(みや)びの心を
思い出したりするものでございますよ。
|