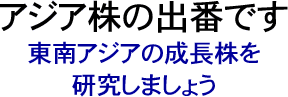|
第69回
通貨危機を振返ると
為替は、
短期的にはわれわれの予測を超えたところで
投機的な動きをします。
しかし、長期的にはその国の成長に合わせて
通貨が強くなるように見受けらます。
そう考えれば
円が値打ちのあるうちに、
出稼ぎに出しておくべきという考えがでてきます。
うまくいけば企業成長の果実以外に
為替変動での果実も得られるかもしれません。
1997年のアジア危機は、
突然降って沸いたように思われる方が多いのですが、
実際は過大評価された通貨が一度に下げ、
それも投機的な勢いがついて、「どーん」と下げた現象です。
経常収支を見てみると、
1994〜5年で東南アジア諸国や韓国の赤字が
急に増えていることがわかります。
データでは為替を下げるべきと思われる数値が出ていました。
1996年頃に実際にバンコックの繊維街のプラトーナムを歩けば、
中国や他国からの買出しの人が激減しているのを
見ることができたはずです。
株価について見ても一部の機関投資家は
1994年頃からもう、帰り支度を始めていたのです。
先日、タイのある会社の社長さんとお話していて
「みんなが政府の言うことを信じていた」と
くやしそうにおっしゃっておられました。
為替は政府によって高く決めることはできますが、
輸入を制限できない市場ではいずれ赤字が累積します。
アジア株に投資をして、
またアジア危機のようなことになったら困ります。
しかし、実際はアジア危機の状態になるまでに
撤退するくらいの用心深さを身に着けておくべきと
思われますし、実際そういう人もおられました。
今、各国はお金が足りなくなった時に備えて、
共通の基金を設けようとしています。
用心に越したことはありません。
強くなる通貨、弱くなる通貨は
貿易収支や外貨準備高の増減を見ていればある程度想像はつきます。
幸い、2003年春現在では
アジアでは貿易収支や外貨準備高が
極端に減少している国はなさそうです。
|